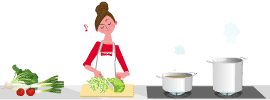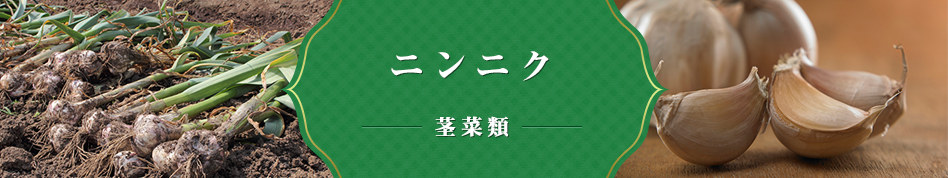肉や魚の臭み消しや、風味付けなどに使う香味野菜として、様々な料理に欠かせないニンニク。
食欲をそそる独特の香りはアリシンと言う成分による物で、殺菌・抗菌作用があり、ビタミンB1の吸収を助けると言われています。
中央アジア原産で、基本的には冷涼な気候を好みますが、関東地方以西の暖地でも栽培できます。その場合、温暖な気候でも育つ「平戸」、「紫々丸」などの暖地系の品種を選びましょう。
東北地方以北の寒冷地向きの品種では、寒地系の「ホワイト六片」、「ニューホワイト6片」などが知られています。通常のニンニクに比べて香りが強くない「無臭ニンニク」は、分類上ではニンニクとは別種のリーキと言う野菜。越冬して太らせた球根がニンニクに似ていたことから名付けられ、比較的地域を問わずに栽培できます。


- 温暖地沖縄・九州・四国
- 中間地中国・近畿・中部・関東
- 寒冷地北陸・東北・北海道
※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。
標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。
お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。
 ニンニクを作るのに必要な資材
ニンニクを作るのに必要な資材
-
-

-

-

-
ニンニクを育てるコツ
栽培期間が8~9ヵ月と長いため、土作りが重要。
水はけが悪いと病気になりやすいので、10cm程度土を盛り上げた、やや高めの畝を作りましょう。
栽培する地域の気候に適した品種を選ぶことも、失敗なく育てるポイントです。
ニンニクの植え付け
植え付け適期は、9月下旬~10月下旬。植え付けの1週間前までに、苦土石灰100~150g/㎡をまいてよく耕しましょう。
植え付け当日は、栽培スペースの中央に深さ20cm、幅15cmの溝を掘り、元肥となる堆肥2kg/㎡、化成肥料100g/㎡をまいて土をかぶせます。この方法は「溝施肥」と呼ばれ、ゆっくりと肥料が効くことから、栽培期間の長いニンニクにぴったり。土作りが終わったら、畝の中央に支柱などで目印の溝を付け、20cm間隔で1片ずつ球根を仮置きします。とがった方を上にし、球根の上部を深さ2~3cmのところまで押し込み、土をかぶせて水をやりましょう。
ニンニクの管理
- 追肥・土寄せ
-
植え付けの6~8週間後、本葉2~3枚の頃に化成肥料30g/㎡をまき、土寄せをしましょう。その後、年内と翌年の3月以降、月に1回同量を追肥します。冬越し中の1~2月の追肥は不要です。
- 芽かき
-
ひとつの球根からまれに複数の芽が出ることがあります。養分の分散を避けるため、生育の悪い芽を地際で切り取るか、株もとを押さえて引き抜きましょう。
- 摘 蕾
-
5月頃に伸びてくる花茎を放置すると、養分が蕾に取られ球根が太らなくなるため、付け根から切り取りましょう(摘蕾)。切り取った花茎は「ニンニクの芽」として食べられます。
ニンニクの収穫
6月頃、葉の一部が枯れてきたら収穫適期。
収穫は、土の乾いた晴天の日を見計らって行ないます。
周りの土をスコップなどでほぐしてから、付け根を手で持って引き抜き、乾燥させてから保存しましょう。

ニンニクの病害虫
- アブラムシ
-
春になって暖かくなると発生し、新芽や葉に群生して茎や葉の汁を吸います。生育が悪くなるだけではなく、各種ウイルス病を媒介する場合もあるので、早めの対処が必要。粘着テープを押しあてて取り除くか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。
- ヨトウムシ
-
夜行性で日中は株もとに潜み、夜間に葉を食害します。ひどい場合には葉脈を残して葉を食べ尽くしてしまうこともあるため、見つけ次第捕殺しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策できます。
- 葉枯病
-
湿度の高い梅雨時などに多く発生するウイルス病。初めは葉先が変色し、次第に大型の病班が現れて葉が枯れたようになります。風通しをよくし、敷きワラなどをして雨による泥のはね上げを防止することで防除可能。落ちた葉にも菌が残っていることがあるので、確実に処分しましょう。
- 春腐病
-
春頃から増えるウイルス病で、初めは暗緑色をした水浸状の病班ができ、進行すると葉脈に沿って拡大。病班が広がった部分は腐ったようにやわらかくなり、株が倒れたり全体が腐敗したりします。水はけの良い土で育てることで、菌の繁殖を防ぎましょう。
栄養価
ニンニクの独特な香りのもとであるアリシンは、殺菌・抗菌作用があり、疲労回復や滋養強壮に効果があるビタミンB1の吸収を助ける働きを持つ成分。アリシンそのものにも、コレステロール抑制、血液サラサラ効果、冷え性の改善、食欲増進、免疫力向上、二日酔いの改善など、数多くの健康効果があると言われています。
他にも、細胞を正常に整える効果のあるカリウムや各種ビタミン類が含まれ、ニンニクはまさに栄養満点のスタミナ野菜。ただし、食べ過ぎは禁物です。生のままだと刺激が非常に強く、胃腸を傷めるおそれがあります。加熱した物で1日2~3片を目安に。高血圧の人は特に注意しましょう。