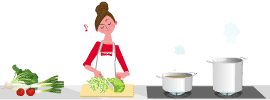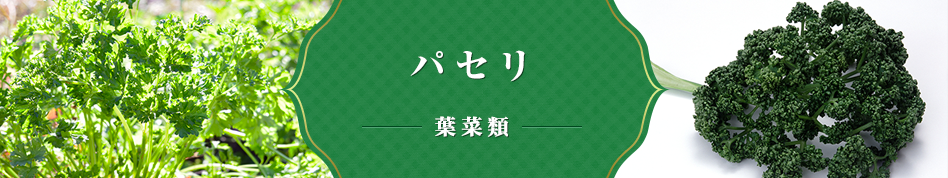くるっと縮れた葉先がかわいらしいパセリ。見た目もさることながら、さわやかな香りも魅力的なハーブの一種です。スープやサラダなどに使えば、香りが料理を引き立てます。
しかし、なかにはその独特な香りが苦手という人も。実はパセリは育て方次第で香りの強さを調整することが可能です。栽培時、日に当てる時間と肥料を少なくすると香りは弱く、反対にすると香りは強くなります。
園芸で好みに合わせたパセリを作って、料理の名脇役として活躍してもらいましょう。


- 温暖地沖縄・九州・四国
- 中間地中国・近畿・中部・関東
- 寒冷地北陸・東北・北海道
※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。
標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。
お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。
 パセリを作るのに必要な資材
パセリを作るのに必要な資材
-
-

-

-

-

-
パセリを育てるコツ
パセリは種から苗に育つまでに長い期間がかかるため、手軽に栽培するなら発芽した苗を購入するのがおすすめです。
また、パセリは夏に健康を損ないやすいので注意が必要。暑い日が続いて苗が乾燥すると、葉が硬くなり、品質が落ちます。そんな夏の乾燥対策として有効なのが、敷きワラ。
株の周囲を敷きワラで覆うことで、地面に直接日光が当たるのを防ぎ、土の湿度を適度に保ってくれます。
パセリの植え付け
植え付けの1週間前に、100g/㎡の苦土石灰、3ℓ/㎡の堆肥、100g/㎡の化成肥料をまいてよく耕し、畝を立てます。複数の畝を立てる場合は、畝の間隔を30cm以上開けるようにしましょう。
植え付け当日、畝の中央に株間30cmで植え穴を作成。苗の根付きが良くなるように、あらかじめ水をたっぷり穴に注ぎます。水が引いたのを確認したら苗をポットから取り出し、穴に植え替え。このとき、根と周囲の土がひとかたまりになった根鉢を崩さないように注意が必要です。最後に株元を軽く押さえ、再度水を与えます。
パセリの管理
- 追 肥
-
植え付けから約1ヵ月後に、最初の追肥を行ないます。1株当たり10g/㎡の化成肥料を株元にまきましょう。収穫後も2週間に1回のペースで、追肥を行なうと長期的に収穫ができます。
- 土寄せ
-
追肥後は必ず土寄せをします。クマデなどを使って肥料と土をよく混ぜ、株元に土を寄せましょう。
- 水やり
-
土の表面が乾きかけてきたら、水を与えます。ただし、水はけが悪いと株の根元から腐ってしまうこともあるので気を付けましょう。
パセリの収穫
収穫を始める目安は、本葉が15枚以上になってからです。外側の葉からハサミで切り取り、10枚ほどは葉が残るように収穫しましょう。
こうすると、初夏から晩秋にかけて、長い期間収穫を楽しめます。

パセリの病害虫
- キアゲハ
-
アゲハチョウの仲間で、主に葉を食害する害虫。その見た目は、幼虫の頃は鳥のフンに似ていて、成熟幼虫になると黒字に橙色の小斑点が目印となります。見つけたら必ず駆除しましょう。
- アブラムシ
-
新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウィルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。
栄養価
飲食店では料理の添え物として登場することの多いパセリ。手を付けない人をしばしば見ますが、パセリは残すのはもったいないほどのビタミン群が含まれています。
ビタミンC・E・Kが豊富ですが、特にビタミンKの量は、あらゆる生鮮食品の中でもトップクラス。ビタミンKには、骨を丈夫にしたり、血液を凝固させ止血したりする働きがあります。
パセリをたかが添え物と軽んじてはいけません。その効用を正しく把握し、積極的に摂取することで、健康維持に大きく貢献してくれます。