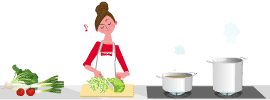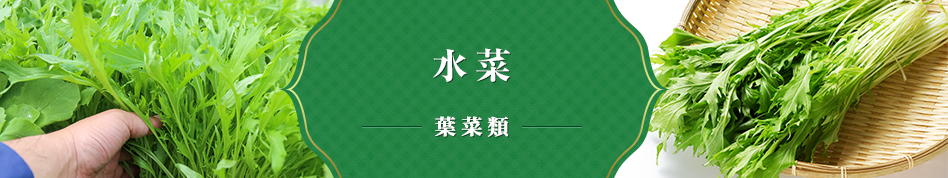水菜は江戸時代からすでに関西で浸透していた、歴史の古い野菜です。京都で水と土だけで作られていたことが、名前の由来と言われています。平成に入ってから日本全国に普及するようになりましたが、水やりを主にする伝統的な栽培方法は昔から変わっていません。水をしっかり与えれば枯れにくいため育てやすく、園芸の初心者にも人気です。
収穫した水菜は、大株と子株で適している料理が異なります。大株は鍋物や漬物、子株はサラダで食べるのが一般的。今回は子株の栽培方法を紹介しますので、たくさん収穫しておいしいサラダを存分に味わいましょう。


- 温暖地沖縄・九州・四国
- 中間地中国・近畿・中部・関東
- 寒冷地北陸・東北・北海道
※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。
標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。
お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。
 水菜を作るのに必要な資材
水菜を作るのに必要な資材
-
-

-

-

-
水菜を育てるコツ
水菜は種から育てるのが一般的。名前の通り水をたくさん吸収しますので、生育初期には水をたっぷりと与え、土を乾かさないことが大切です。
土の表面が乾いたら、すぐに水やりをするようにしましょう。
他にも育成するうえでは、間引きを行ない株間をしっかり開けることと、高温期は害虫が出やすいので防虫ネットなどで虫の侵入を防ぐことが重要です。
水菜の種蒔き
種蒔きの2週間前に苦土石灰100~150g/㎡を土に混ぜ、よく耕しておきます。
種蒔きの1週間前に堆肥2kg/㎡、化成肥料200g/㎡を散布し、さらに耕しましょう。
種蒔き当日は幅60~70cm、高さ10cmの畝を作り、深さ1cmのまき溝を作ります。複数の畝を作る場合は、条間20~30cmが目安です。種は株間1cmでまき、土を埋め戻してたっぷり水やりをします。
水菜の管理
- 間引き
-
種蒔き後、3、4日で発芽し始めます。種蒔き後の約7日目には双葉が開き、本葉が見え始めたら株間が3~4cmに広がるように間引きをしましょう。間引き後は軽く土寄せをします。
- 追 肥
-
草丈7〜8 cm、本葉4枚程度のときに、化成肥料30g/㎡を追肥し、株元を軽く耕して土寄せします。その後は週に1回程度を目安に、同量の追肥をしましょう。
- 水やり
-
発芽するまでは、土が乾かないように水をこまめに与えます。乾燥に弱く、寒さには強い野菜のため、冬の間も十分に水を与えましょう。土の乾き過ぎは生育不良の原因となります。
- 除 草
-
雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。
水菜の収穫
草丈が25~30cmになったら、順次根から引き抜いて収穫します。
種蒔きから収穫までかかる日数は、春蒔き、秋蒔きが30~40日、夏蒔きが25~30日が目安です。

水菜の病害虫
- 根コブ病
-
根にコブができ、吸水が阻害される病気です。病気の初期は、葉がしおれたり、治ったりを繰り返し、症状が進むと枯死してしまいます。アブラナ科の野菜を連作すると発生率が上がるので気を付けましょう。発生してしまったら、感染した株は腐敗しないうちに抜き取って処分し、畑には土壌殺菌剤などを散布します。
- 立枯病
-
株全体の生育が悪くなり、病気が進行すると下葉から徐々に黄色くなり、やがて株全体が立ち枯れを起こします。連作を避けることが、予防策として効果的。立枯病の病原菌は土壌で繁殖するので、この病気が発生した場合は株を抜き取って処分しましょう。
- ヨトウムシ
-
主に夜間に活動するヨトウムシ。葉裏に生み付けられた卵がふ化すると、群棲して葉肉部を食害します。成長すると葉を食べ尽くすようになり、被害が拡大。ふ化直後の葉裏に群棲しているときに、まとめて駆除しましょう。
- アブラムシ
-
新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウィルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。
栄養価
水菜はβ-カロテン、ビタミンC・E、カルシウム、鉄分などが含まれた栄養価に優れた野菜です。ビタミンCには免疫力を高めたり、ストレスを緩和したりする働きがあり、様々な病気を予防。特に風邪の予防には効果的と言われているため、風邪が流行る時期は水菜を積極的に食べましょう。
調理法は生食のサラダがおすすめ。煮たり焼いたりすると、熱に弱いビタミンCが損なわれるためです。また食前には、油性ドレッシングをかけましょう。油はβ-カロテンの体内への吸収を促進させます。
なお、水菜のサラダはシャキシャキとした食感で葉応えが抜群。サラダにすると栄養面だけではなく、おいしさもさらにアップします。