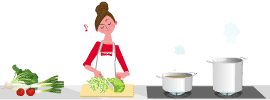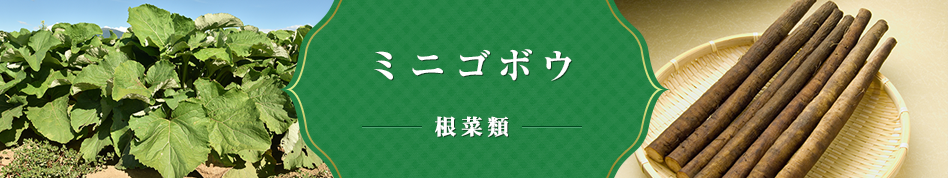キク科の直根類で、ほのかな土の香りが楽しめるゴボウ。縄文から平安時代の間に日本に伝わって、大昔から人々の食生活に根付いていました。その品種は長さ75cm~1mの長ゴボウと、長さ35~45cmのミニゴボウの二種が代表的です。
園芸では根が深くまで伸びる長ゴボウより、根があまり伸びないミニゴボウが初心者にはおすすめ。
手軽に栽培して、定番のきんぴらやサラダを作り、おいしく頂きましょう。


- 温暖地沖縄・九州・四国
- 中間地中国・近畿・中部・関東
- 寒冷地北陸・東北・北海道
※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。
標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。
お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。
 ミニゴボウを作るのに必要な資材
ミニゴボウを作るのに必要な資材
-
-

-

-

-
ミニゴボウを育てるコツ
根が伸びる途中に硬い物に当たると、根が枝分かれする「又根」の原因になります。
30cm以上に掘ってしっかり耕し、石や土などの塊を取り除きます。
ミニゴボウの種蒔き
種蒔きの1週間前、100~150g/㎡の苦土石灰をまき、酸性度をph6.0~6.5に調整します。皮が硬いゴボウの種は、そのままでは発芽しにくいため、一晩水に浸しておきましょう。こうすると皮が水を通しやすくなるため、発芽率が上昇します。
種蒔き当日は、3ℓ/㎡の堆肥、100g/㎡の化成肥料を施して耕し、幅約60cmの畝を作成。畝の中央に深さ0.5~1cmのまき溝を作り、株間1cmで種をまきます。ミニゴボウの種は発芽に光を必要とする好光性種子のため、土を薄めに埋め戻して軽く押さえましょう。最後は土の表面が乾かないように、畝全体にたっぷりと水を与えます。
ミニゴボウの管理
- 間引き
-
間引きは計3回で、株間の距離を目安にして行ないましょう。双葉が開いたら株間約3cm、本葉が3~4枚になったら株間5~6cm、本葉が5~6枚になったら株間10~15cmまで広げます。
- 追 肥
-
追肥は2回目の間引き後から行ないます。30g/㎡の化成肥料をまき、その後も2週間に1回のペースで追肥をしましょう。追肥の際は、雑草をついでに抜いておくと効率的です。
- 土寄せ
-
1回目の間引き後、残した株がぐらつかないよう、周囲の土を寄せて支えます。2回目の間引き、追肥後は、クワなどで肥料と土を混ぜて株元に寄せましょう。それ以降も、土の表面が固くなってきたら株の周囲を軽く耕し、土をやわらかくしておきます。
- 水やり
-
土が乾燥すると発芽しにくいので、水はしっかりと与えます。水を勢いよく与えると種が流れてしまうことがあるため、水やりは優しく行ないましょう。
ミニゴボウの収穫
収穫適期は、種蒔きから80~90日後、根元の太さ1.5cm程度が目安。
土中に深く埋まったゴボウはいきなり引き抜くと折れやすいため、まずは根の周囲を掘り、土をやわらかくしてから引き抜きましょう。

ミニゴボウの病害虫
- 黒斑病
-
野菜がこの病気に感染すると、まず葉に褐色の円形病斑が発症。放っておくと大きな病斑がいくつもできて葉が縮み、下葉から黒く枯れていきます。発生初期に病葉を摘み取る、収穫後に病葉を集める、といった方法で対策をしましょう。
- うどんこ病
-
うどん粉をまいたような白色のカビが葉や茎に円形に生え、次第に全体に広がります。光合成が阻害される他、葉の養分が吸収されて生育不良になり、花が咲かない、果実が肥大しないなどの害があるため、発生初期に薬剤を散布して対策しましょう。また、窒素過多がうどんこ病の原因になるため、肥料を与えるときは注意が必要です。
- ゴボウヒゲナガアブラムシ
-
幼虫は赤褐色、成虫は黒褐色になる大型アブラムシです。新芽や葉に寄生し、春から秋の長期間にかけて発生。特に発芽したばかりの頃に寄生されると、その後の成長が著しく阻害されます。なお、この害虫はモザイク病を媒介するので注意が必要。早期に薬剤を散布し、防除を行ないましょう。
栄養価
ミニゴボウには、食物繊維、カリウム、カルシウム、マグネシウムなど豊富な栄養が含まれています。
なかでも注目したいのが食物繊維。ミニゴボウに含まれる食物繊維の量は、野菜のなかでもトップクラスです。食物繊維は、血糖値の上昇を抑える、胃の中で膨れて食べ過ぎを防止する、便秘を解消する、善玉菌を増やして腸内環境を整えるなど、健康維持やダイエットにうれしい効果が満載。なお、食物繊維は水分と一緒に摂取すると働きが良くなるので、ゴボウを食べるときには水分をしっかり摂るようにしましょう。
また、ミニゴボウの皮には抗酸化作用が期待できるポリフェノールがたっぷり含まれています。収穫したてのミニゴボウなら、たわしなどで軽くこすって洗うだけで栄養たっぷりの皮までおいしく食べることが可能です。