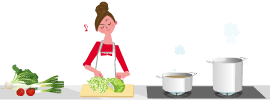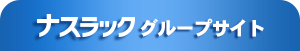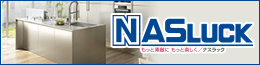お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
食品の基礎知識
身近なあの料理の起源や、初めて登場したエピソードなどをご紹介します。
おせちは「御節」と書き、中国大陸から伝わった暦上の節目、季節の変わり目などにあたる節日(せちにち、節句)を意味します。
節日にはみんなでお祝いし、このとき作られる料理が、「御節料理」と呼ばれました。
元々は「年迎え」の膳として、大晦日に食べる物でしたが、現在ではほとんどの地方で元日以降に食べるのが一般的となりました。ただし、一部の地方には、かつての名残りで大晦日に食べる風習がまだ残っています。

日本では幕末になるまで、仏教の戒律などのため一般には牛肉を食べることはありませんでしたが、「すきやき」と称された料理はすでに存在していました。
1643年刊行の料理書「料理物語」に「杉やき」が登場しており、これは鯛などの魚介類と野菜を杉材の箱に入れて味噌煮にする料理と書かれています。江戸後期に入ると各文献ですき焼きに関する具体的な記述が見られるようになり、そこでは使い古した田畑を耕す農具の鋤(すき)を火にかざして鴨などの鶏肉や、あるいは鯨肉などを加熱する一種の焼肉と記されています。この魚介類の味噌煮の「杉やき」と、鶏肉や鯨肉を焼いた「鋤やき」という二種類の料理が、牛肉の鍋物としての「すき焼き」の起源と言われています。
また、一説では「すき身」の肉を使うことから「すき焼き」と呼ばれるようになったとも言われています。

「天ぷら」は代表的な日本料理のひとつと思われがちですが、その起源はヨーロッパにあり、安土桃山時代にキリスト教の宣教師と共に渡来した南蛮料理の一種と言われています。
日本にキリスト教を布教したフランシスコ・ザビエルが来日した年が1549年で、この頃に日本に伝わった説が有力視されています。
「天ぷら」の語源は、キリスト教の四句節「クアトロ・テンプラシ」からきているとされています。この四句節には、信者がキリストの受難をしのび、節食したり、肉を食べない習わしで、日本のキリシタンの間にも広まり、「クアトロ・テンプラシ」から転じて、魚の揚げ物料理のことを「天ぷら」と呼ぶようになったと言われています。
また西日本では、天ぷらは薩摩揚げのことを意味する地域もあります。

ファストフードとして代表的なハンバーガー。映画などにもよく登場し、欧米文化の象徴的な食べ物としてイメージされていますが、起源はモンゴルとされています。
11世紀頃のロシア東部にあるタタール地方は騎馬民族の住む土地で、羊の肉をパテ状に固め、皮に包んで鞍の下において食べた習慣がありました。それが蒙古のモスクワ侵攻でロシアに伝えられ、羊肉を牛肉に代えて、タマネギと卵を加えた物が「タルタルステーキ」として誕生しました。これが当時世界で有数の港だったドイツ・ハンブルグに伝わり、そこからヨーロッパ全体に広まったとされています。
アメリカに伝わったのは19世紀の終わり頃で、ドイツからの移民がハンブルグ・ステーキと呼んでいたのを、英語発音で「ハンバーグ・ステーキ」と呼ぶようになり、アメリカ全土で大変な人気となりました。
1904年にセントルイスの近くにある小さな町である男がハンバーグをパンに挟んで売り出したところ、とても人気を呼び、当時セントルイスで開かれていた世界博覧会にスタンドを出して販売したところ、大好評を博しました。そののちに今のようなバーンズスタイルに改良され、世界で愛されるファストフードに成長しました。