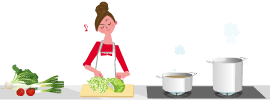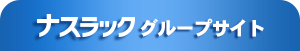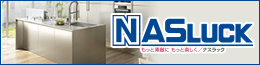お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
健康な食生活を始めよう
近年、私たちの「食」への関心は高まっています。平成13年に食品衛生法が改定されて、加工食品にアレルギー物質の表示が義務付けられたのも、その表れかもしれません。
食物アレルギーは、特定の食べ物に対して過敏に反応してしまう病気で、患者は乳児に多く見られます。私たちの健康のためにも、そして成長していく子どものためにも、食物アレルギーにはきちんと対処していきましょう。
| 乳児 | 10% |
|---|---|
| 3歳児 | 4~5% |
| 学童期 | 2~3% |
| 成人 | 1~2% |
(出典:厚生労働省 リウマチ・アレルギー対策委員会 平成17年報告書)

食物アレルギーの原因になりやすい食品は、年齢によって異なる傾向があります。
乳児の頃は「鶏卵・乳製品・小麦」が、成人では「甲殻類・小麦・果物類・魚類・そば」が原因になりやすいようです。以下の25品目については、加工食品のアレルギー表示が食品衛生法によって義務化または推奨されています。
- 表示が義務付けられている5品目
- 卵・乳・小麦・そば・落花生
- 表示が推奨されている20品目
- アワビ、イカ、イクラ、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、サケ、サバ、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マツタケ、桃、山芋、リンゴ

特徴
乳児の10人に1人が食物アレルギーを起こしたことがあり、その中で最も多いのはアトピー性皮膚炎など皮膚に現れる症状です。
また、乳幼児までに原因となった食物アレルギー物質には、加齢とともに耐性を得ると言われていますが、成人になってからも原因となってしまう物質に対しては耐性が得にくいようです。
症状
じんましんや湿疹、結膜充血、腹痛、くしゃみ、呼吸困難などの、皮膚粘膜症状、消化器症状、呼吸器症状があります。
ひどい場合には、「アナフィラキシー」と言う、命にかかわる危険な症状に陥ることもあります。
- 「アナフィラキシー」とは?
- 「アナフィラキシー」とは、全身で起こるアレルギー反応のことです。症状にはじんましん、腹痛、呼吸困難などがあり、重症になると血圧低下などでショック症状が現れ、生命に危険が及ぶこともあります。
また、食物アレルギーの原因となる食品を食べてから、すぐに激しい運動をすると起こる、「アナフィラキシー(食物依存性運動誘発性アナフィラキシー)」にも注意しましょう。
対処法としては、「アナフィラキシー」を起こす可能性がある、または以前に起こしたことがある場合は、対処方法をまわりの人に伝えておくと良いでしょう。また、もしも起こってしまったら、すぐに病院に行って治療をしてもらいましょう。
食物アレルギーの原因となる食品の摂取を避けることが一番の対処法となりますので、まずは医師の診察をきちんと受けて原因となる食品を特定することが大切です。
ただし、健康的な生活をするためには、栄養バランスの良い食事をすることが必要です。原因となる食品を避けることは前提ですが、それだけでは栄養の偏った食事になる危険があります。代わりとなる食材を使うなど、料理に一工夫加えて、栄養バランスの取れた食事をするように心がけましょう。