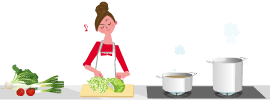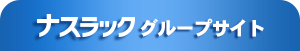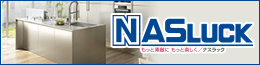お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
健康な食生活を始めよう
食中毒は夏だけでなく、1年中発生するものです。近年では、住宅の密閉性が高まり、暖房なども完備されていることから季節を問わず発生しています。
しかし、食べ物が腐りやすい夏場には、当然その発生数は多くなります。食中毒はどのようにして発生するのでしょうか?
食中毒にはいくつかの種類があります。毒キノコやフグの毒などによる「自然毒食中毒」、メタノールなどによる「化学物質食中毒」、細菌やウイルスなどによる「細菌性食中毒」の3種類です。
このうちの大半が細菌性食中毒です。食中毒を引き起こす細菌やウイルスが、生鮮食品や調理器具、人の皮膚などに付着し、集団で発生することが多いのが特徴です。

食中毒の主な症状
食中毒の症状は種類や原因となる細菌などによって異なりますが、多くの場合は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢、発熱などを伴います。
中には髄膜炎(ずいまくえん)や敗血症などの重症の病気を引き起こすものもあるので、注意が必要です。
食中毒にかかると、体内の水分が失われ、脱水症状を起こす危険性があります。下痢や嘔吐、発熱などが起きた場合には、お茶やスポーツドリンクなどで、十分に水分を補給するようにします。
なお、食中毒の病状に似ている場合は、なるべく早く病院の診察を受け、その指示に従いましょう。
細菌性食中毒の主な原因菌としては、患者数の多い順に「サルモネラ」、「カンピロバクター」、「ウエルシュ菌」、「腸炎ビブリオ」、「黄色ブドウ球菌」などがあります。

サルモネラ
肉類や卵などに付着している細菌で、十分に加熱することで死滅します。75℃以上の高温で1分間以上加熱したり、生肉を扱った手や調理器具を十分に洗うことで予防できます。
カンピロバクター
肉類、特に鶏肉に付着している細菌で、十分に加熱することで死滅します。生食用の食品以外は、75℃以上の高温で、1分間以上加熱するようにしましょう。
また、サルモネラの場合と同様に、生肉を扱った手や調理器具からの感染も考えられますので、十分に手を洗って清潔な状態を保つようにしましょう。

ウエルシュ菌
肉類や根菜類に付着している細菌です。カレーやシチューなどを大量に作った場合などに発生しやすいので、注意が必要です。
特に、温度が50℃程度に下がった状態で繁殖しやすく、再加熱した場合でも、十分に加熱ができていないと、食中毒を引き起こす恐れがありますので、注意が必要です。
カレーやシチューなどを大量に作って保存する場合には、密閉容器に小分けして、冷蔵庫で保存するようにしましょう。また、食べる前には、よく混ぜながらしっかり加熱すると、感染を防ぐことができます。
腸炎ビブリオ
魚介類に付着している細菌です。海水温が17℃程度になると活発に活動を始めます。熱や真水に弱いですが、冷凍しても細菌が生き残るので注意が必要です。
また、増殖のスピードが速いので、購入後はできるだけ早く冷蔵庫へ入れるようにしましょう。
黄色ブドウ球菌
人の皮膚や鼻腔(びくう)などに存在する細菌で、特に傷がある部分に多く集まります。
調理する人の手から食品に付着して、食中毒が起こるケースもあるので、手洗いをこまめに行ない、清潔にしておくことが大切です。
食中毒を引き起こす細菌は、食品や料理によって異なります。いくら気を付けていても、食中毒にかかってしまうこともあります。ここでは、食品別の注意点を紹介します。

肉類
代表的な食中毒を引き起こす細菌であるサルモネラやカンピロバクターは、肉類などに付着しています。
どちらも十分に加熱することで死滅するため、生食用の物以外は、必ず75℃以上の高熱で1分間以上加熱するようにしましょう。
特に、鶏肉のささみの湯通しやハンバーグを作る際には、赤い部分や肉汁が残らないよう、中までしっかり加熱することが大切です。
卵
卵に付着しているサルモネラは、しっかり加熱すれば死滅します。ゆでる場合には、半熟より固ゆでの方が安心です。また、生で食べる場合は、必ず賞味期限内の新鮮な物を使いましょう。
なお、殻にひびが入った卵は、サルモネラが付着しやすいので、すぐに処分するようにしましょう。また、殻の外にも細菌が付着している場合があるので、パックごと冷蔵庫で保存すると良いでしょう。

魚介類
魚介類に付着している細菌・腸炎ビブリオは、繁殖するスピードが速いので、購入後はすぐに冷蔵庫に入れるようにしましょう。また、冷凍してある物については、冷蔵庫で解凍するようにしましょう。
調理する場合には、塩水ではなく真水で洗ってから、しっかり加熱すると良いでしょう。
お弁当、おにぎり、サンドイッチ
お弁当やおにぎり、サンドイッチなど、手を使って調理した物は、黄色ブドウ球菌が付着して、食中毒にかかる可能性があります。調理をする際には、できるだけ素手で行なうことを避け、使い捨て手袋などを使うようにしましょう。
また、食べ物から出た蒸気や水分が多いと、細菌が繁殖しやすいため、お弁当を詰める際には、よく冷ましてから蓋を閉めるようにしましょう。
まずは、基本である家庭のキッチン環境を見直すことです。食中毒予防のポイントは、「細菌を付けない、増やさない、殺す」の3つです。
特に、食品の保存方法、キッチンの環境を見直すことで、食中毒にかかる恐れを減らすことができます。
冷蔵庫の使い方を見直そう
冷蔵庫に物を詰め込み過ぎると、冷気がうまく循環せず、庫内の温度が上昇し、細菌やウイルスが繁殖しやすい状態になります。食中毒を防ぐためには、冷蔵庫で保存する食品の量を容量の7割程度にして、賞味期限が切れた物を処分すると良いでしょう。
また、こまめに掃除や消毒を行なうことも大切です。

手や調理器具はきちんと洗う
料理を作る前にきれいに手を洗うのは鉄則ですが、肉や魚、卵など、細菌が付着しやすい食材を扱ったら、その都度、手を洗うことが大切です。
また、それらを調理するために使った包丁やまな板などの道具も、一度洗ってから他の食品を切るようにしましょう。
なお、手指に傷がある場合には、必ず使い捨て手袋をするようにしましょう。
キッチンまわりをいつも清潔に
細菌が繁殖しやすい包丁、まな板、ふきん、スポンジなどは、使ったあとすぐに洗剤と流水で洗い、清潔な状態を保つように心がけましょう。
洗った道具は、水気を切ってしっかりと乾燥させることが大切です。また、漂白剤などで定期的に殺菌をしておくと安心です。