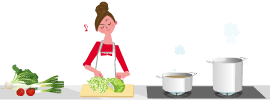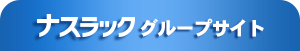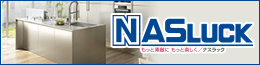お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
健康な食生活を始めよう
食について考える習慣や食に関する様々な知識、食を選択する判断力などを、楽しく身に付ける方法をご紹介します。

私たちは野菜や肉・魚などを食べて、健康を維持したり、身体を成長させたりしています。しかし毎日摂る食事に対して、それ程強い関心を持つことはあまりありません。
その一方、ダイエットなどでカロリー摂取に過剰に反応したり、サプリメントで一部の栄養素だけを偏って摂取したりするなど、食の乱れが多く見られます。
食育は、普段の食生活を見直して正しい食の知識を身に付けるとともに、食の安全性や流通の仕組みにも目を向けた大切な学習です。

特に子供がいる家庭では、健やかな成長を促す上で大切な教育と言えます。食育を日常生活に取り入れ、ライフスタイルに役立てましょう。
食べることは、生きていく上で重要な行為です。食育は食べることに重点を置いた教育で、食生活を通じて健康を維持し、日本人としての食文化を知ることができます。
食生活が豊かな現代では、いろいろな食材や食品が手軽に入手できるようになりましたが、その一方で生活習慣病など健康を妨げることも多くなりました。普段食べている物をよく考えて、食材や摂取方法などを再確認してみましょう。
食育の考え方
中国では、古くから食は健康に通じると考えられ「医食同源」という言葉が生まれました。それだけ食べることの意味を重視してきたと言えます。
食育も生活の観点から食べることを重視し、食に関する知識を身に付けることにあります。国でも食育を奨励しており、その基本的な考え方は、国民すべてが健全な食生活を実現して健康の維持・増進を図り、日本人としての食文化を継承することで、食についての正しい知識を身に付けるよう学ぶことにあります。
私たちが普段食べている食事や摂取方法などを見つめ直し、身体のためにバランス良く栄養を摂取しているか、食材の栄養を活かした調理をしているかなどを知ることで、健やかな生活を送ることを目的としています。

食育の歴史

平成17年6月に「食育基本法」が制定され、食育の必要性が法制化されました。しかし、それ以前にも食育という考え方はありました。
食育という言葉が最初に使われたのは明治時代で、軍医だった石塚左玄が「体育も智育も才育も、すべて食育であると認識すべき」と、人間の心身は食から作られると訴えました。
また同時期に活躍した小説家の村井弦齋も、自らの小説「食道楽」で、子供の成長には体育や知育よりも食育が先であることを記しています。
食育がすべての教育の源であるという考え方は、100年以上も前に提唱されていました。物が豊富で食の情報が多い現代こそ、もう一度食について正しく学ぶことが求められています。