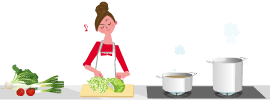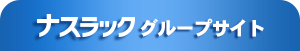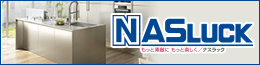お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
健康な食生活を始めよう
食について考える習慣や食に関する様々な知識、食を選択する判断力などを、楽しく身に付ける方法をご紹介します。
スーパーなどでは、野菜や果物・肉類・魚介類など、年中いろいろな食材が並んでいます。食材そのものだけでなく、多くの加工品や調理品も販売され、私たちもそれらを買って食べています。
普段何気なく食べている食材や食品ですが、これらがどのようなルートで私たちの食卓に並ぶか、旬の時期以外にどのように作られているかを少し意識してみましょう。意識することで食への関心が高まり、食育を積極的に進めることとなります。

食の流通を知る

私たちが食べている米や野菜は、生産者から農協などを通じて市場に出回り、スーパーや小売店などで販売されます。パンや豆腐・麺類・菓子類などは、食品メーカー(食品製造業)が原料を仕入れ、厳しい安全基準の下で独自に加工し、全国に出荷されます。
こうした食品の流通は、交通アクセスや保存方法が発達したことで、日本国内だけでなく海外からもいろいろな食品が集められ、全国に届けられています。
インターネットの時代を迎えた現代では、個人でも生産者から直接食品を買うことができるようになりました。
また外食産業など飲食店では、確かな食材を安く仕入れるため独自に流通システムを作っているケースもあります。このように食品流通経路は多様化しています。
地域の食文化を知る
世界的に見ると日本は小さな島国ですが、それでも気候や地形が異なり、各地にそれぞれ特色があります。
そのため、その土地によって栽培される物、獲れる物が違い、味付けや調理方法も変わってきます。
これらはその土地で育まれた固有の食生活であり、古くから土地の住民によって伝えられてきた食文化でもあります。その中で名産や特産物と呼ばれる品々が全国に広まって、多くの人から重宝がられました。
今でこそ、自宅にいながらにして、全国各地の名産を容易に食べることができますが、本来はその土地に行って味わい、風土や歴史を感じることが日本の食文化を知る第一歩となります。

食糧事情を知る

日本は、様々な食料を輸入に頼っています。食料消費に対して自国でどのくらい生産できているかを表す食料自給率で見ると、日本は昭和40年度以来減少の一途をたどり、主食用穀物自給率は、ここ10年程40%程度の横ばいで推移しています。
こうした背景には、これまで自給可能な食生活から、年々冷凍食品や加工食品へと変化していることが挙げられます。これらの食品の原料は安価な輸入品を使用していることが多く、自給率の低下を招いています。
また、国産の農産物の需要が低下することで、農地面積や生産者の数も減少し、食糧供給基盤そのものが低下していることも挙げられます。