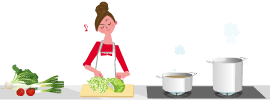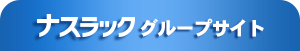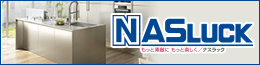お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
健康な食生活を始めよう
正しい食生活の基本は、1日3回朝・昼・晩と規則正しく食事を摂ることです。食事内容も、栄養面、カロリー面ともに偏りがないように気を付けましょう。
しかし、現代社会において、様々な理由から、それが困難になることも少なくありません。結果、健康を害することにも…。
いつまでも健康で楽しい食生活を送り続けるためにも、体に良い食事バランスを知り、日頃から理想的な食事ができるよう心がけましょう。

理想的な食事のバランスを保つためには、様々な食品を組み合わせて食べることが大切です。
本来、日本人はご飯などの主食と、野菜・いも類・きのこを使った副菜、そして肉や魚などを使った主菜といった食物を、上手に組み合わせて食べてきました。
しかし、欧米型の食事が主流となりつつある現在、日本古来の食事様式は崩れつつあります。昨今、メタボリック・シンドロームに該当する人々が増加しています。血糖値や血圧が高めの中高年や、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病を患っている子どもたちは、食生活の乱れが原因と言われています。
このことは、深刻な健康問題になっており、政府は平成17年6月、厚生労働省と農林水産省による、国民の健全な食生活の実現を目的とした「食事バランスガイド」を発表しました。
| 主食 | ご飯、パン、麺類など、炭水化物の供給源となるものを5~7品。 |
|---|---|
| 主菜 | 肉、魚、卵、大豆や大豆製品など、タンパク質や脂質を含む食材を使った料理から3~5品。 |
| 副菜 | ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含む、野菜、イモ、大豆以外の豆類、きのこ、海藻などを使った料理から5~6品。 |
| 牛乳、乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズなど、カルシウムの多い食材を2品。 |
| 果物 | ビタミンCやカリウムを多く含むフルーツを2品。 |
栄養素もカロリーも、1日に必要な量を1日3回の食事でバランス良く摂ることが大切です。1日に必要なカロリーは成人男性の場合、約1,907~2,225Kcalです。この場合、1回の食事で摂取する理想のカロリーは636~742Kcalになります。これを毎日3回、決まった時間に、ほぼ同量ずつ摂るようにしましょう。不足しがちな栄養素は、サプリメントなどの栄養補助食品などで補う方法もあります。
ここでは、厚生労働省と農林水産省による「食事バランスガイド」で推奨されている内容から、1日のメニュー例を紹介します。
主食・副菜・主菜に加え、牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品と果物の5グループから、炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル・食物繊維などを、過不足のないように組み合わせていくことが大切です。
以下の朝・昼・晩のメニュー例を参考に、普段の食生活を見直してみましょう。

朝食
| 主食 | ご飯(小)2杯 |
|---|---|
| 主菜 | 目玉焼き |
| 副菜 | ひじきの煮物 |
| 果物 | ミカン1個 |
ついつい簡単になってしまったり、抜いてしまいがちな朝食ですが、1日の最初に摂るエネルギー源であり、特に脳の働きを活性化させるためには、欠かせないものです。
お米など穀物の主成分である糖質は、速効性のあるエネルギー源になり、糖質の分解によってできるブドウ糖は、脳の活性化に効果的です。さらに、卵などに多く含まれるタンパク質には、体温を上昇させ血行を良くする機能があり、寝起きの体を目覚めさせてくれます。また、ミネラルや食物繊維を多く含むひじきなどの海藻類は、整腸作用を促します。

昼食
| 主食 | ご飯(小)2杯 |
|---|---|
| 主菜 | ハンバーグ1/2 |
| 副菜 | 野菜スープ、野菜サラダ |
| 牛乳・ 乳製品 |
チーズ1枚、ミルクコーヒー1杯 |
昼食は、どうしても外食が多くなりがちですが、ラーメンや丼などの単品料理はできるだけ避け、栄養バランスの整った定食などを選びましょう。
また朝食同様、午後からの活力を支える大切なエネルギー源となります。炭水化物を摂取することで、午後からの運動エネルギーを貯えることができます。
肉類や乳製品など高タンパクな食材を摂るのなら、昼食に取り入れるのが最適です。そのとき、ホウレンソウやニンジンなどの緑黄色野菜、キャベツや白菜などの淡色野菜、これらを組み合わせて食べましょう。
野菜はスープなど火に通すと食べやすくなり、たくさん食べることができます。野菜に多く含まれるビタミン類は、糖質を効率良く燃焼させエネルギー源を生み出します。

夕食
| 主食 | ご飯(小)2杯 |
|---|---|
| 主菜 | サンマの塩焼き1/2切れ、冷奴1/3丁 |
| 副菜 | 筑前煮、ホウレンソウのおひたし |
| 果物 | リンゴ(小)1/2個 |
1日を締めくくる夕食は、朝食や昼食で不足した栄養を補うよう心がけましょう。
しかし、就寝前に食べ過ぎて胃もたれなどを起こさないよう、ボリュームを抑えることも大切です。そのためには、油分を控えた和食中心のメニューが理想的と言われています。