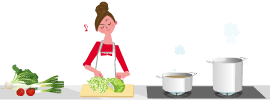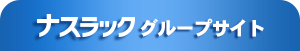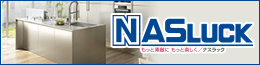お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
テーブルマナーの心得
季節の恵みを大切にし、おもてなしの心で仕上げる和食。この美しい料理にふさわしいマナーを身に付けることで、さらに一品一品をおいしく頂くことができます。そして、料理を通して和の心を身に付け、豊かなひとときを過ごしましょう。
和食は、食膳の形式によって「本膳料理」「懐石料理」「会席料理」に分けることができます。それぞれ料理の出し方や順序は異なりますが、共通して言えることは、盛り付けの美しい形を崩さないように食べることです。
日本の正式なご馳走【本膳料理】
室町時代に武家の礼法から生まれた、日本で最も格式高い料理です。正式には足付きのお膳で、本膳・二の膳・三の膳といった流れで料理が出され、品数も3汁11菜と決められています。現在ではあまり見かけることはありませんが、冠婚葬祭や皇室の儀式などにその形式が息づいています。

茶席で出される軽食【懐石料理】
茶懐石料理とも言い、茶道とともに発展した、茶席の前に軽く腹ごしらえをするための料理で、江戸時代に生まれました。元々の由来は、禅宗の修行僧が朝昼の2食しか食べなかったため、夜に空腹と寒さをしのぐために、温石(おんじゃく)を懐に入れ空腹をまぎらわしたことに起因しています。料理には質素ながら一期一会の心が込められています。
※正式には、大きな器に盛られた料理を順に回し、自分の分を取って食べます。
最も身近な和食【会席料理】
江戸時代から伝わる料理で、現在の和食の主流となっています。会席料理は、本膳料理や懐石料理といった料理の形式を表すものではなく、これらの品を酒宴の席で出す饗宴料理として伝えられました。
元々はできたての料理を一品ずつ配膳する形式ですが、現在では一度に料理が並ぶ場合もあります。宴席などで食べる和食として定着しています。
箸や器の使い方から料理の食べ方まで、基本的な和食の作法をご紹介します。かしこまった席でもぎこちなくならないよう、普段の食事から気を付けましょう。

和食の基本、箸の使い方
箸を正しく扱うことは、和食をスマートに頂く基本です。普段の食事から気を付けることで、自然に美しいマナーが身に付きます。
- 割り箸を割るときは両手で持ち、平行に分かれるように割ります。手に取るときは、右手でそっと持ち上げて下から左手を添えます。
- 右手を右端へ滑らせながら、下から受けるように持ち直します。
- 箸を置くときは、逆の手順で行ないます。箸置きではなく箸袋の場合は、箸袋を千代結びにして箸の先をその中に隠し、食後は箸袋の中に戻しましょう。
タブーとされる箸使い一例
- 箸で器を引き寄せる「寄せ箸」
- 箸を器の上に置く「渡し箸」
- 箸先をなめる「ねぶり箸」
- どの料理を取るか、器の上で箸をウロウロさせる「迷い箸」
- いったん取りかけてから、他の料理に箸を移す「移り箸」
- 箸を料理に突き刺して食べる「刺し箸」
キレイに見せる器の扱い方
- 手に持つ器
- てんぷら・刺身・焼き魚などを盛り付けた「平皿」、煮物・炊き物などを盛り付けた「大鉢」以外の器は手に持ちましょう。 刺身しょうゆが入った小皿も、受け皿として手に取って使います。
- 蓋の付いた器
- 左手を器に添えて右手で蓋を取り、裏に付いた水滴を器の中に落としてから、裏返して置きます。裏返して重ねると塗りや装飾を傷つけることもあるので、食べ終えたあと、蓋はもとのように器に重ねます。
- 煮物
- 里芋など滑りやすいものは、片方の箸で刺し、もう片方の箸で挟んでもかまわないとされています。
- 焼き魚
- 頭の方から尻尾の方へ食べ進め、上の身を食べ終えたら骨の下に箸を入れて外し、下の身を食べます。骨や皮などは1ヵ所にまとめておきます。
- 串焼き
- 串先を皿に付けて、飛び散らないようゆっくり串から外して食べます。