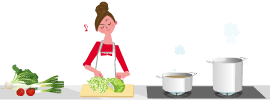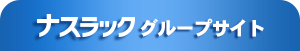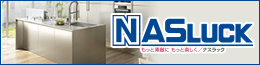お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
全国の郷土料理
日本には、各地に伝わる様々な料理があります。そこには、「特産物をさらにおいしく食べたい」、「冬の厳しさを少しでも和らげたい」、「限られた食材を無駄なく食べたい」など、先人たちの見事な工夫と食に対する強い思いが詰まっています。
ここでは、昔から大切に育まれ、愛されてきた郷土料理の数々をご紹介します。

【滋賀県】 フナ寿司
琵琶湖産のニゴロブナを利用する料理で、その歴史は千年以上も遡ります。もともとは発酵を利用し、保存に適した「熟れ寿司」として普及しました。
熟れ寿司はお寿司の原点とされ、押し寿司、ばら寿司、握り寿司と発展していきました。
作り方は、ニゴロブナのうろこを取り、内臓を抜いた腹に塩を詰めて3ヵ月程塩漬けします。その後、水洗いして干してからご飯と一緒に漬け込み、さらに数ヵ月発酵させてできあがりです。

【京都府】 おこうこのじゃこ煮
京都、滋賀地方に伝わる家庭料理です。「おこうこ」とは香の物、特にたくあんを指します。
色が悪くなったり傷んだたくあんを使うのが特長で、たくあんを塩抜きして煮たて、削り節やじゃこなどを入れて汁気がなくなるまで煮て作ります。
やわらかいため、普通のたくあんが硬くて食べにくいお年寄りにも喜ばれます。何でもおいしく頂くための、知恵が詰まった料理です。

【大阪府】 小田巻き蒸し
茶碗蒸しの中に、うどんを入れた料理です。
元禄年間、唐人から長崎に伝わり、それが大阪に伝播した物とされています。消化がとても良く、体が芯から温まるため、冬季に食されます。ただし、昔は茶碗蒸しを作るのに手間がかかるので、高価でなじみの薄い料理でした。
最近では、電子レンジを使ったレシピが普及しており、受験生の夜食など家庭で手軽に作られるようになりました。

【兵庫県】 出石皿そば
2~3口程度のそばを盛った小皿を5皿程度並べ、薬味を入れたつゆに浸して食べます。
江戸中期、出石藩主が鞍替えとなり、新藩主となった信州仙石氏によって広まりました。幕末期には、手塩皿にそばを盛る、持ち運びに便利な割子そばのスタイルをなし、屋台料理として普及します。
昭和30年代に出石皿そばと呼ばれるようになり、現在ではお皿の芸術性も楽しみのひとつとなっています。

【奈良県】 飛鳥鍋
飛鳥時代、唐の僧侶がこの地に渡来し、冬の寒さをしのぐために考案されたと伝えられている牛乳入りの鍋料理です。僧侶の間でひそかに鶏肉を入れて食され、徐々に庶民に広まっていきました。現在は牛乳を使いますが、当時は山羊の乳を使っていました。
食材は、鶏肉や白菜・春菊・シイタケ・豆腐など一般的な鍋料理と同じで、牛乳独特のまろやかな味と風味を堪能できます。

【和歌山県】 めはり寿司
ソフトボール程のおむすびを、高菜の浅漬けの葉でくるんだ料理で、山仕事や畑仕事の間に食べるお弁当として、古くから親しまれています。
食べるときに目を見張る程大きな口を開けなくてはならないとか、目を見張る程おいしいから、などが語源と言われています。
最近ではゴマやじゃこ、かつお節など、中の具材のバリエーションも広がり、一般家庭はもちろん、コンビニで販売される程人気が出ています。