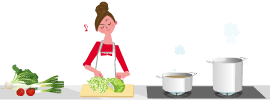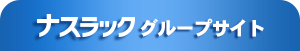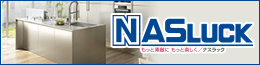お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
全国の郷土料理
日本には、各地に伝わる様々な料理があります。そこには、「特産物をさらにおいしく食べたい」、「冬の厳しさを少しでも和らげたい」、「限られた食材を無駄なく食べたい」など、先人たちの見事な工夫と食に対する強い思いが詰まっています。
ここでは、昔から大切に育まれ、愛されてきた郷土料理の数々をご紹介します。

【徳島県】 祖谷(いや)そば
祖谷地方は水はけの良い急斜面が多く、昼夜の寒暖の差も多いため、そば栽培に適しています。ここで収穫される、そばを使った郷土料理が祖谷そばです。
こしがあって太めで短く、薫り高いのが特長です。だしは、いりこと薄めのしょうゆでとり、汁ごとかき込むような感覚で食べます。
そばを打つときに、つなぎをほとんど使わないため、「縁が切れる」につながるとして、婚礼のときは出されません。

【香川県】 てっぱい
讃岐地方は、大小の溜め池が点在しています。
昔、農繁期が終わると、ため池に棲んでいたフナを獲って食べていました。その代表的な料理が「てっぱい」です。語源は「鉄砲和え」が変化したものという説が有力です。
白味噌・砂糖・酢などを混ぜた調味料に、塩もみしたダイコンとフナの切り身を和えて食べます。最近ではフナが入手しにくくなったため、サバやコノシロが代用されます。

【愛媛県】 ふかの湯ざらし
南予地方に伝わる漁師料理です。昔この地方ではふか(鮫)がよく釣りあげられましたが、売り物にならないため漁師が酒の肴にするために考案したのが始まりです。
皮付きのまま、三枚におろしたあと湯水に通して、酢味噌などで食べます。淡白な味に味噌の辛味が調和して、食欲を増進させます。
豆腐やこんにゃく、キュウリなどを添えることもあり、今では冠婚葬祭に欠かせない料理となっています。

【高知県】 どろめ
イワシの稚魚を指すどろめは、この地ではほぼ1年中獲れるため、酒の肴として重宝されている珍味です。
食べ方はそのまま三杯酢で浸けるか、たまりじょうゆに、おろしショウガ・ネギを入れるケースが一般的です。
透き通った身がコリコリして、爽快なのど越しが楽しめます。また、ちりめんのように釜揚げし、しょうゆで味付けして雑炊にしたり、お吸い物に入れたりと、様々な調理法があります。