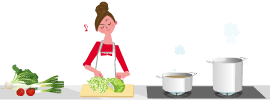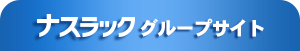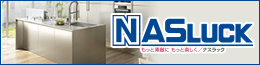お役立ち情報
料理やキッチンに関する豆知識や裏ワザなどをご紹介します。
全国の郷土料理
日本には、各地に伝わる様々な料理があります。そこには、「特産物をさらにおいしく食べたい」、「冬の厳しさを少しでも和らげたい」、「限られた食材を無駄なく食べたい」など、先人たちの見事な工夫と食に対する強い思いが詰まっています。
ここでは、昔から大切に育まれ、愛されてきた郷土料理の数々をご紹介します。

【福岡県】 エツ料理
エツとは、日本では有明海にのみ生息するカタクチイワシ科の珍しい魚のことです。体長は20~30cm程で、晩春になると産卵のために有明海に注ぐ筑後川を遡上するため、そこを刺し網で漁獲します。
エツを使った料理は、洗い・塩焼き・天ぷらなどがあり、料亭などで食べられる他、川舟で獲れたてを味わう舟遊びのコースも人気があります。地元では初夏を告げる季節料理となっています。

【佐賀県】 だぶ
唐津市に伝わる、具だくさんの煮物です。語源は、「だしをたくさん使って、ざぶざぶ作る」がなまったものなど、諸説あります。
材料は鶏肉やキクラゲ・干しシイタケ・タケノコなど多彩で、冠婚葬祭やお客様向けの物と、自宅用で若干違いがあります。
お客様用には、こんにゃくを一度凍らせて乾燥させた「凍りごんにゃく」を使います。これは、この料理にしか使わない珍しい食材で、ふわっとした独特の食感が特長です。

【長崎県】 ヒカド
ヒカドとは、ポルトガル語で「細かく刻む」という意味です。元々は宣教師や貿易商人たちが食していた物を、長崎の料理人が改良したのが始まりです。
作り方は、その名の通り魚や野菜を1.5cm程のサイコロ状に切り刻み、しょうゆなどでじっくりと煮込みます。さらに、すりおろしたサツマイモを入れ、甘みととろみを付けます。
和風のシチューのようで、心身ともに温めてくれる素朴な料理です。

【熊本県】 辛子レンコン
17世紀、熊本藩主・細川忠利氏が病に伏した際、豊前の国の僧がレンコンを食べるよう勧めました。
すると藩士の一人が、加藤清正公が熊本城の外堀に栽培していたレンコンに和辛子粉を混ぜた麦味噌を詰め、衣を付けて揚げた物を献上したところ、細川氏はとても喜びました。
これが辛子レンコンの始まりで、江戸時代は門外不出としていましたが、明治維新を機に製法が広く伝わり、熊本の名物として広まりました。

【大分県】 みとりおこわ
あずきに似た、1cm程の大きさの黒い「みとり豆(ささげの一種)」を使った郷土料理です。
みとり豆を塩水でゆで、ひと晩水に浸けたもち米と一緒にせいろで蒸し、ゴマ塩をかけて食べるのが一般的です。豆の皮に程良い弾力があり、もち米と一緒に食べることにより、もち米のやわらかさと豆の歯ごたえが楽しめます。
主に宇佐市の長洲地区で、お盆の時期に家庭で食べられます。

【宮崎県】 冷や汁
鎌倉時代の文献に登場する、古くから親しまれてきた農民の料理です。埼玉や山形にも伝えられていますが、宮崎県の物が当時の冷や汁に一番近いと言われています。
元々は、農家が繁忙期に簡単に調理できることから広まりましたが、第二次大戦後は一般家庭にも普及し、今では様々な形で食されています。一般的には、いりこやアジの身をすり、豆腐やキュウリなどを混ぜて冷やした物を温かいご飯にかけて食べます。

【鹿児島県】 酒寿司
薩摩藩・島津家の当主が、宴会の残り料理と飯にお酒をかけたら、翌日に良い香りが漂っていたことがきっかけと言われています。
そのため、寿司と言っても酢を使わず、地酒でしめて作ります。タイ・エビ・イカなどの海の幸、タケノコ・フキなどの山の幸をたっぷり使う、豪華で華やかな伝統料理です。
長時間仕込む手間がかかるため、大切なお客様をもてなすときによく出されます。

【沖縄県】 豆腐よう
琉球王朝時代に中国から伝わった料理で、起源は明国の腐乳と言われています。島豆腐という木綿豆腐を、米麹・紅麹・泡盛などを使った漬け汁で発酵・熟成させた物で、特に酒の肴に出されます。
完成するのに半年程必要なうえ、熟練の技術が求められる難しい料理ですが、栄養価が高く健康食品でもあるので、上流貴族の間で高く称賛されていました。
味は東洋のチーズと表現され、濃厚な味わいが特長です。