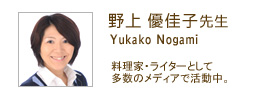こんにちは、料理家の野上優佳子です。
もうすぐ、ひな祭り
我が家も毎年、娘達のために、ひな人形を飾ります。
私が生まれたときに祖母がくれた、七段飾りのおひな様。世代を継いで飾れることを、とてもうれしく思います。
ひな祭りのメニューは、「潮汁」や「ちらし寿司」が定番でしょう。
ちらし寿司のルーツを探ると、江戸時代の事典「守貞謾稿(もりさだまんこう)」に、「箱に納めた飯と具を入れた押し寿司の中でも、シイタケの醤油煮を間にはさみ、上に卵焼きやタイやアワビの薄片といった複数の具を幾何学的に並べ置いたもの」 として、「こけら寿司」が登場しています。
「こけら寿司」とは、表面に魚肉片などの具をちらした寿司を指します。
新しく建てられた劇場の初公演の「こけら落とし」、そのこけらと同じく「木くず」という意味。
魚肉片を木くずに見立て、その名がついたようです。
その一方で、「箱寿司」がルーツだとも。
箱寿司には、底が抜ける「押し抜き」型と、底を抜かずに箱に詰めたまま箸などで掘り起こす「すくい寿司」「おこし寿司」があります。
この箱寿司をきれいに掘り起こすのは大変、また食べるときは結局崩して食べるわけで。
ならば、最初からくずしたまま皿に盛りつけよう、つまり押し寿司の簡略化の完成形である、という解説も。
寛政期(1700年代終わり)の料理本「海鰻百珍(はむひやくちん)」「名飯部類(めいはんぶるい)」などには、飯に具を混ぜ込み、皿に盛りつける形の寿司が紹介されています
明治時代の東京の風俗が分かる「東京年中行事」 には、ひな壇の供え物として、御膳(赤豆飯、蛤赤味噌仕立て、焼き物、なます)と肴(卵焼き、赤白鹿の子蒲鉾、豆くわい、巻き寿司、赤貝汁)が書かれていますが、ちらし寿司は登場しません。
戦前〜戦後の昭和の文献にやっと、「五目寿司はごちそう」として各家庭で作られ、ひな祭りのときに食べたという記述を見つけることができました
地方によって大きな違いはあるでしょうが、ちらし寿司とひな祭りの組み合わせは、意外と歴史が浅いものかもしれませんね。
さて今回は、ちらし寿司に彩りを添える「桜でんぶ」の作り方をご紹介します。
手作りのものは、市販とは一味違い、格別のおいしさ!意外と簡単にできるので、ぜひ試して下さいね