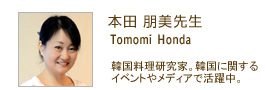こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
韓国では生まれたときから天に召すときまで、「もち」が振る舞われる機会が多く、生活に欠かせない食べ物のひとつになっています
その歴史は古く、部族国家時代(紀元前1世紀から紀元2世紀ごろ)にはすでに、もちが存在していたと言われています。
その理由に部族国家時代の遺跡から、甑(こしき)という米などを蒸すための土器が発見されています
当時のもちは米、アワ、大豆、麦、キビなどからできており、天を祭る儀式のために使われました。
そのいくつかは今日(こんにち)まで継承されており、現代でも様々な儀式にもちが使用されています。
さらに三国時代(紀元4世紀から7世紀ごろ)には稲作が盛んになったことで、もちも発達していきます。
「三国史記」には年末にもちを作る風習があったという記述が残っており、さらに「三国遺事(さんごくいじ)」という史書にはもちが供物として使用されたという記述も残されています。
ときは流れ、現代では供物て使用するだけではなく、日常生活でもおやつや朝夕晩の食事などで、もちを食べるようになりました。
今でも韓国では、人生の節目や節日(せつにち)に必ず用意されるもちがあります。
今回はそのいくつかをご紹介します
【生後100日記念・ペクソルギ】
医療が発達しておらず生後100日を超えることが難しかった時代に、無事に100日を迎えられた赤ちゃんをお祝いする風習がありました。
医療の発達した今でも、この100日のお祝いは受け継がれており、そのときに食べるのが「ペクソルギ」です
ペクには「白」と「百」の意味があり、純真無垢に長生きしてほしいという思いが込められています。
ソルギは米粉で作った蒸しパンのようなもちで、米粉のもちはケーキのような形に作りやすいので、お誕生日や結婚式などのお祝いのときに、もちケーキとしてよく登場します
この米粉のもちは、歴史の中で一番古くからある物です。
【正月(ソルラル)・トックク】
日本と同様に、韓国でもトッククという雑煮をお正月に頂きます。
日本と異なるのは、もちがもち米ではなく米粉(うるち米の粉)からできているので伸びにくいことです。
薄い楕円形で小判のような形をしていることから、お金持ちになれるようにといった願いも込められています。
また韓国は現在でも、数(かぞ)えで年齢を数えています。
そのため、お正月はトックク(雑煮)を食べる日でもあり、必ず全員が年を重ねる日でもあるのです
【端午(タノ)・スリトック】
旧暦の5月5日にあたる端午は、太陽 の光が一番強い日と考えられていたため、豊作を祈願する日でもあります。
の光が一番強い日と考えられていたため、豊作を祈願する日でもあります。
摘んだよもぎを混ぜ込んだもちの表面に、車輪模様のような形を表面に型取ったもちが「スリトック」です。
梅雨の直前であるこの時期は、昔は病気が流行しやすかったため、厄払いの食材であるよもぎを使って災厄を祓(はら)うといった意味がありました。
【秋夕(チュソク)・ソンピョン】
秋夕は日本では中秋(ちゅうしゅう)の名月と呼ばれる日で、旧暦のお盆にあたることから、韓国ではお墓を掃除しご先祖様へ感謝する日でもあります
秋夕にはソンピョンという、米粉を練って成形した生地の中にゴマ、栗、豆などのアンを入れ、松葉を敷いた蒸し器で蒸したもちを作り、お供えをするのが昔からの習わしです。
このソンピョンは、秋の収穫に感謝する気持ちを込め、その年に穫れた早生の新米と穀物で作られます。
その他にも韓国には色々なもちや、もちにまつわる行事がありますので、またの機会にご紹介したいと思います
楽しみにしていて下さいね
さて本日のレシピは、韓国語でウォンソビョンと言う「もち入りのハチミツ水」です。
もちの中にはナツメとゆず茶のアンが入っており、爽やかな味わいのもちです。
今回は伝統的なレシピをご紹介していますが、ここに果物を入れてフルーツポンチ仕立てにしてもおいしいですよ。
夏にぴったりのデザートですのでぜひお試し下さい