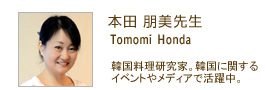2020/02/26
こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です

近年韓国の台所は、日本と同様に電力化が進み、ますます便利になっています。
とは言え、冬の寒さが厳しい韓国では、「温突(オンドル)」と言う床暖房施設が5世紀頃の三国時代からあったため、昔の台所事情が日本とは異なりました

今回は、「韓国における台所の変遷」について、各時代ごとにご紹介したいと思います


 三国時代
三国時代温突のある台所は、土間が他の部屋よりも一段低い場所にあります

と言うのも、温突は、薪や藁をくべて煮炊きしたときに発生した煙を、床下の煙道に通すことで床が温まる仕組みと、煙道が「¬」の字形で、家の片隅にある仕組みであるため、台所は温突と切り離せないからです。
そのため、冬は暖房代わりとして、調理をしないときでも火を焚き、床下は板石で土台を築き、きちんと火災予防の対策も取られていました。
ちなみに、韓国では台所のことを「釜屋(プオク)」と言います。
 高麗時代
高麗時代三国時代に貴族の家庭だけで使用されていた温突は、この頃には庶民にも普及されます

 朝鮮時代
朝鮮時代釜屋が家の中心に置かれ、各部屋に煙道が通るようになります。
食器棚には食器や燃料を置いたり、水瓶を備え付けて水を保管したりするため、中二階を作る場合も多くありました

釜屋の釜台は、「飯釜」や「汁釜」など、2〜3つに分けられた大釜が設置され、その大釜は鉄製で熱伝導が遅い一方、一度熱くなると冷めにくいため、重宝されます

また、大釜でご飯を炊くときは、米の中心に味付けした卵液をいれた容器を置き、ご飯と一緒に茶碗蒸しを作るといった工夫がなされていました

さらに、大釜の蓋は、持ち手を下に向けて、魚やチヂミを焼くフライパンとしても使用されたそうです

ちなみに、貴族階級の家には、台所の横にチャンバンと言う納戸を設置し、祭器などを保管しました。
 現代
現代温突は、台所機能がなくなり、床暖房だけが受け継がれていますが、床暖房は温水を循環させる仕組みへと変わりました。
日本も昔は土間の台所でしたが、暖房設備は囲炉裏やコタツですよね

それぞれの文化の違いは、知れば知るほどおもしろいです

さて、本日のレシピは、大釜の蓋で焼くチヂミ「レンコン海鮮チヂミ」をご紹介致します

通常は酢醤油で頂くのですが、知り合いの韓国料理店のシェフから、塩で食べるチヂミを教えて頂きましたので、今回採用しました。
皆さんも、ぜひお試し下さい