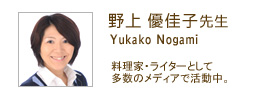本年もよろしくお願い申し上げます。
料理家の野上優佳子です。
今年も皆様に、楽しくておいしくて、そして「へえ、そうなんだ  」 と思って頂ける話題をご提供できたらと思っております。
」 と思って頂ける話題をご提供できたらと思っております。
新年も幕を開け、新春の初売りも落ち着いた頃、毎年恒例で開催されるのが
「全国駅弁大会」です。
全国各地のデパートの催事場などで開催され、テレビのニュース等にも取り上げられますね。
寒くなってバーゲンも終えて客足が遠のく時期にお客さんを呼び込む目玉催事、今がまさにシーズン真っ盛りです。
その中でも「日本一  」と呼び声高いのが東京・新宿にある某百貨店の
」と呼び声高いのが東京・新宿にある某百貨店の
『元祖有名駅弁と全国うまいもの大会』。
1966年から始まり来年には開催50回目を迎える予定のこの大会、昨年は250を超える駅弁が集まり、来場者数は延べ約100万人とも言われています。
日本に鉄道が開通したのは、明治5年
5月に品川駅—横浜駅間(現在の桜木町駅)で仮開通したあと、10月には新橋駅—横浜駅間で正式に運行が始まりました。
では「駅弁の発祥はどこか?」と言えば、これは、「明治10年に栃木県宇都宮駅で、竹皮に包んだ梅干し入りのごま塩握り飯 にタクアン付きがホームで販売された」いう説があります(定かではありません)が、少なくとも明治20年代には全国各地に登場しています。
にタクアン付きがホームで販売された」いう説があります(定かではありません)が、少なくとも明治20年代には全国各地に登場しています。
明治に発し今も私たちが食べられる駅弁の代表格が、静岡県静岡駅で販売されている
「元祖鯛めし 」 。
」 。
桜飯の上に鯛のそぼろが全面敷き詰められたその駅弁は、明治25年に発案され、明治30年(1897年)に「上等御弁当鯛飯」として販売されました。
すぐに大変な人気を集め、現在も変わらぬ静岡名物駅弁として愛され120年を迎えようとしています。
ちなみに駅弁は、鯛めしのように単品の食材をメインにして、名前にもその食材を前面に打ち出した物は「特殊弁当」、ご飯を中心に様々なおかずが入って名前も「幕の内弁当」や「お弁当」、と言うものは「普通弁当」と2つに大別されるそうです。
さて今回は、お弁当の副菜として大活躍!
作りおきおかずにおすすめの「干しシイタケの含め煮」をご紹介します。
年末年始に購入して残っている干しシイタケはありませんか?
このレシピで、ぜひお試し下さいね。