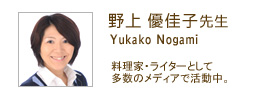こんにちは、料理家の野上優佳子です。
寒さ は続いているものの、梅の花も咲き誇り、少しずつ春の気配 
なんだか胸がワクワク します。
ウグイスの声はもう聞かれましたか?
ウグイスと言えば春告鳥とも呼ばれ、まさに春の使者。
ウグイス色とは、この鳥の羽の色にちなんだ言葉で、緑褐色のことです。
春に芽吹く草木の色を思わせる美しい色ですよね。
食文化の中の「ウグイス」を見てみましょう 。
今では使われなくなってしまった【切匙】(せっかい)という台所道具があります。
これはすり鉢やすりこぎに粘り着いた物をかき落す木製の道具で、シャモジを縦半分に割ったような形をしていました。
これをかつて宮中に仕えていた女房たちは「ウグイス」と呼んだそうです。
料理という面では「ウグイス豆」が思い浮かびます。
青エンドウ豆を甘く煮た物で、それを「こしあん」にした物が「ウグイス餡」。
ウグイス豆は山形県では「冨貴豆」(ふうきまめ)とも呼ばれます。
あんこを求肥でくるみ小鳥に見立てて楕円に成型した和菓子を「うぐいす餅」と呼びますが、それは餅にウグイス粉(青大豆で作られたきな粉)をまぶすためです。
このうぐいす餅の名付け親は、豊臣秀吉と言われています。
うぐいす餅は、奈良県で400年続く老舗和菓子店が発祥です。 豊臣秀長が、兄である豊臣秀吉をもてなす茶会を催す際に「何か珍菓を作れ」と命じたところ、当時の店主菊屋治兵衛が粒餡を餅で包んできな粉をまぶした餅菓子を献上したところ、秀吉が大変気に入り「うぐいす餅」と名付けた、と残されています 。
豊臣秀長が、兄である豊臣秀吉をもてなす茶会を催す際に「何か珍菓を作れ」と命じたところ、当時の店主菊屋治兵衛が粒餡を餅で包んできな粉をまぶした餅菓子を献上したところ、秀吉が大変気に入り「うぐいす餅」と名付けた、と残されています 。
その名が語り継がれ、季節の鳥の名にちなんでいることから、今ではうぐいす餅は初春の和菓子 として定着したというわけです 。
なかなか風情ある素敵なお話ですね。
さて今回は、ウグイス粉の原料である青大豆を使ったレシピ「ひたし豆」をご紹介します。
東北地方の郷土料理のひとつで、数の子等と一緒に漬けておせち料理などにも登場する物です。
青大豆はつまり枝豆を乾燥させた物ですので、これを戻しだしに漬けて作ります。
素朴ながら深みのある味わいのヘルシーフード、ぜひお試し下さいね。