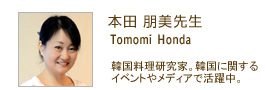こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
韓国料理にも、食べる物は薬になると言う『薬食同源』の考えが根付いていて、それを象徴する料理があります。
甘いおこわの『薬食(ヤクシク)』です。
おこわですが、食事よりもデザート感覚で頂く物です。
 歴史が非常に古い食べ物で、伝説にも登場します。
歴史が非常に古い食べ物で、伝説にも登場します。
新羅時代の488年、第21代の王の命が狙われる事件が起こり、王様が鳥、ネズミ、豚に救われました そこで、正月の最初に迎える亥、子、午日は厳かに過ごし、さらには午日である旧暦1月15日には、黒いおこわを作って鳥に捧げたと伝えられています。
そこで、正月の最初に迎える亥、子、午日は厳かに過ごし、さらには午日である旧暦1月15日には、黒いおこわを作って鳥に捧げたと伝えられています。
旧暦1月15日はテボルムと言います。一年で最初の満月の日を祝い、その年の無病息災と豊作の願いを込めて催す行事で、韓国では重要な節日です。
そして、現在でもテボルムに作るものが「薬食」です。または、薬飯(ヤクパプ)とも言います。
新羅時代は、ご飯に鳥の好きな「なつめ」のみ入っていましたが、今ではしょうゆ・黒砂糖・栗・松の実・ゴマ油・シナモンなどが入り、漢方食材をふんだんに使った豪華な物になりました
ここで、二つの漢方食材の効能をお伝えしますね。
 なつめ
なつめ
中国では「1日3粒なつめを食べると歳を取らない」ということわざがある程、老化予防に良いと言われています。
干しなつめは、鉄分、カリウム、カルシウム、食物繊維が豊富。気と血を補強するので、胃腸などの機能を調え体調を改善させてくれる上、血を増やすので貧血にも良く体に潤いを与え、さらには精神を安定させる。体を温める働きもあるので冷え性予防に良く、利尿作用によりむくみを改善する。
そんな効能から、韓国の医学では「大棗(たいそう)」と言う生薬として使用しています。
 シナモン
シナモン
シナモンの生薬名を、桂皮(ケイヒ)と言います。
桂皮はクスノキ科トンキンニッケイや同属植物の樹皮を乾燥した物。身体を温める働きに優れています。冷え性で体力が落ちている場合、桂皮を摂取すると血液循環が良くなり、身体の機能を高めます。特に胃や下腹部に働きかけるので、食欲不振を改善し、生理痛の痛みを緩和します。
薬食は、名前の通りまさに薬になるご飯ですね 
もちろん本日のレシピは『薬食』 。本来は蒸し器で作りますが、炊飯器で簡単に作れる方法をお伝え致します