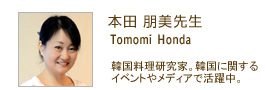こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
韓国旅行の目的として、グルメや観光の他に食器店巡りも楽しみのひとつです。
中でも韓国の白磁や青磁に魅了され、思わずおみやげにたくさん購入してしまう方は少なくないようです
青磁とは青磁釉を使った磁器のことで、翡翠色を帯びた色合いの磁器です。
高麗では青磁色を「翡色(ピセク)」と呼び、中国では「秘色(ヒソク)」と言われる程、神秘の色と評されていました。
もともと青磁は紀元前に中国で生まれ発達した物で、朝鮮半島には11世紀に宋から伝わりました。
青磁が朝鮮半島で発達した背景には、高麗時代の食生活水準が上がったことが深くかかわっています。
また青磁は観賞用としてだけではなく、実用的な食器も多く作られてきました。中には香炉など緻密なものも生み出され、上品な青い色合いは、高麗時代の仏教文化に融合し、伝来元の宋とは一線を画し独自の発展を遂げました。
形、釉薬、質などをかけあわせることで、種類は増加します。
のちに、表面に文様を付けたり、色違いの土や銀などを埋め込んだりして焼き上げる象嵌青磁が盛んになりました。
その後、高麗時代の後期には、白磁が少しずつ焼かれるようになり、朝鮮王朝時代の白磁への発展に繋がります。
そのため高麗青磁は、白磁の基礎とも言えるのです
全羅南道(チョルラナムド)の康津(カンジン)では、10世紀から14世紀まで青磁が盛んに作られ、いまも16の窯が残っています。
国宝級の青磁は、康津で作られたものが八割を占めるとか。
また、夏になると康津青磁祭りが開催されるため、一般の方たちも制作体験ができるそうです。
同じ食べ物でも盛り付ける器によって、見た目でおいしさが変わりますよね。
特に青磁には独特の風合いがあるので、いつものメニューも少し違った雰囲気に見えるはずです
また韓国料理を載せると料理が上品に見えるので、韓国料理作りに興味のある方にもおすすめです
本日のレシピは、イカのネギ巻きです。
青磁の器に盛り付けると、イカの白が映えますよ