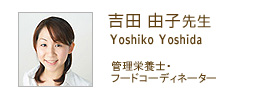こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。
7月の行事に「七夕」がありますね
七夕の行事食と言えば「そうめん」です。
地域によって違いがありますが、七夕にそうめんを食べる風習が全国各地にあります。
これは、中国伝来の「索餅(さくべい)」という小麦粉料理を、7月7日に食べると1年間無病息災で過ごせるという伝説があることから、奈良時代に宮中行事に取り入れられたのが始まりと言われています。
その後、索餅がそうめんへと変化し、現代では7月7日の七夕にそうめんを食べるようになったと言われています。
また、そうめんの細い糸のような見た目から、織姫の織り糸に見立てられたなど諸説はいろいろあります。
そうめんが七夕の行事食であるからだけでなく、気温が高くなるこの時期は、そうめんなどの冷たい麺料理がおいしく感じられますね
そこで今回のブログは夏においしい「乾麺」についてご紹介します。

乾麺とは、呼んで字のごとく乾燥させた麺類のことです。 乾麺類JAS規格(任意法)・乾麺類品質表示基準(強制法)によると、「小麦粉、そば粉または小麦粉もしくはそば粉に大麦粉、米粉、粉茶、卵類を加えた物に食塩、水など(かんすいを除く)を加えて練り合わせたのち、製麺し、乾燥した物」と定義されています。
乾麺類JAS規格(任意法)・乾麺類品質表示基準(強制法)によると、「小麦粉、そば粉または小麦粉もしくはそば粉に大麦粉、米粉、粉茶、卵類を加えた物に食塩、水など(かんすいを除く)を加えて練り合わせたのち、製麺し、乾燥した物」と定義されています。
乾麺の製法は、昔はすべて手作業でしたが、近年は機械化が進んでいます。
乾麺は、ざっと大きく分けて昔ながらの手作業の製法の物を「手延べ干しめん」、機械製の物を「乾麺類」と呼んで区別しています。
また乾麺は、そば、うどん、きしめん、ひやむぎ、そうめんなどに分類されます。
そばはそば粉を使用した物と分類されますが、上記に挙げたそば以外の4種は、JAS規格が制定される以前は不明確でした。
例えば、「ひやむぎ」は1寸の幅に麺線(めんせん)が18本から22本入る物で、「そうめん」は24本以上入る物といった具合に、おおむねその本数になる物で分類していたそうです。
びっくりですよね
現在は麺の太さによって、以下のような基準があります。
・干しうどん・・・長径1.7mm以上
・きしめん・・・幅4.5mm以上、厚さ2.0mm未満
・ひやむぎ・・・長径1.3mm以上、1.7mm未満
・そうめん・・・長径1.3mm未満
(※長径とは、楕円の二つの軸のうち長い方の軸を指します)
ただし、例外もあります。
例えば、徳島名産の「半田そうめん」のように、JAS規格ではひやむぎに相当する太さでも、長年使われてきた名称を尊重し、そうめんという名称が使われる場合もあるようです。
そうめんだと思って何気なく食べている乾麺は、もしかしたらひやむぎかもしれませんね
乾麺を購入する際は、その太さに注目してみましょう。
好みの麺の太さが分かれば、名称に惑わされることなく選べますよ
さて、今回は『夏野菜の冷やし麻婆そうめん』をご紹介します。
冷たいそうめんに冷たい麻婆だれをかけた、暑くて食欲のない日でも食べやすい、ボリュームのある一品です。
試してみて下さいね