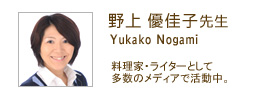こんにちは、料理家の野上優佳子です。
今年はお弁当やお酒のおつまみなど、これまでに計4冊の本を執筆させて頂きました
本に載せるお料理の写真撮影で、楽しみのひとつになっていたのが、スタイリストさんに用意して頂く「うつわ」です。
毎回、レシピ本の制作に入る前には、本のコンセプトやイメージ、実際に作るお料理のラインアップをお伝えしておきます。
すると、それに合わせてスタイリストさんが、食器や小道具を選んでおいて下さるのですが、それらのステキなこと
用意された食器や小道具を使って盛り付けられたお料理は、いつもとまた違った温かみや、上品さ、素朴さなど、その本のコンセプトに合った雰囲気に仕上がるのです。
こういったときに、「うつわや小道具もお料理の一部なのね 」と改めて思います。
」と改めて思います。
そんなお料理の名脇役とも言えるうつわの中で、私が特に好きなのが日本製のやきものです。
レシピ本に載せる写真の撮影準備では、スタジオに運ばれていくうつわを眺めてることが多く、スタイリストさんにいろいろ質問したり、気に入った物を見つけると購入先などを聞いて後日探しに出かけたりしています。
そんな私の大好きなやきものについて、今回は少しお話しをしましょう

やきものには、原料や焼き方などの違いから大きく土器、陶器、磁器、炻器(せっき)の4種類に分けられると言われています。
【土器】
最も歴史の古い器で、日本では縄文時代に製作がはじまったやきものです。
歴史の勉強でみなさん何度か見かけたことがあるかと思います。
現在は、うつわとして日常的に使われていると言うよりは、歴史的な資料や古美術品となっています。
【陶器】
粘土を原料としていて、見た目にも素朴な土の風合いが感じられるやきものです。
吸水性があるので釉薬(ゆうやく)と呼ばれる、ガラス質の上薬(うわぐすり)がかかっている物が多く、指ではじくと少し鈍い音がします。
うつわの底の部分にある、丸い高台(こうだい)と呼ばれる部分には釉薬がかかっていないことが多いので、原料となった土の色がよく分かります。
【磁器】
陶石や、粘土に陶石を混ぜて作られているので、陶器に比べて地の色が白いやきものです。
一般的には薄くなめらかで、軽いのが特長で、指ではじくと「チン」と金属質の音がします。
4種類の中で、最も固いやきものです。
吸水性がなく丈夫なため、扱いやすいので日常使いのうつわとしても人気があります。
【炻器(せっき)】
鉄分などの不純物を含む粘土が使われていて、陶器と磁器の間のような物です。
素地が白くなく、石のように硬く焼き締まったやきものを指します。
叩くと硬い音がします。
ちなみにこの4種の中で、私たちが日常でよく使っているのが陶器と磁器です。
例えば陶器と言えば土鍋や湯のみ 、茶道に使われる茶器(茶碗)などが、磁器はティーカップやソーサー
、茶道に使われる茶器(茶碗)などが、磁器はティーカップやソーサー 、絵皿などが一般的です。
、絵皿などが一般的です。
普段なにげなく「これがかわいい」、「コレが好き」と選んでいるうつわですが、簡単にこうした特徴を覚えるだけでも選ぶときの楽しさが倍増します。
ちなみに我が家では、ご飯茶碗は使う本人が好きな物を選んで購入しています。
また毎日の食卓の副菜を盛り付ける小鉢代わりの猪口(ちょく)などは、家にあるうつわの中から使う本人が好きな物を選ぶのですが、見ているとそれぞれ好みがあるのがよく分かります
例えば小学生の息子は染付けなどの薄手の磁器を、大学生の次女は粉引(こひき)など素朴な風合いの陶器を好んでいつも選びます。
小さな子供でも、なんとなく「こういった風合いが好き」という感性はあるのだなあ、となかなか興味深いです。
子供たちが自分で選んだうつわでおいしそうに食べている姿を見ると、お気に入りのうつわに盛り付けられたお料理は、いつも以上においしく感じるのかなと思えます

ちなみに私は、有名な作家が作った高級品や、流行のデザイナーがデザインした物でなくとも、自分が愛着を持って使えるうつわだと、お料理をするのが楽しくなります
みなさんは、どんなうつわが好きですか?
さて今回は、旬を迎える枝豆のレシピ、「枝豆のショウガしょうゆ煮」をご紹介します。
塩ゆでもおいしいですが、ショウガしょうゆで煮ると、また違ったおいしさを味わえます
お気に入りの器に盛り付ければ、その味わいはまた格別です
ぜひお試し下さいね。