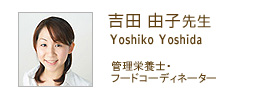こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。
暑い季節は、レタスやキュウリ、トマトなど夏野菜を使ったサラダがおいしいですね
健康のためにも野菜はしっかり摂らないと!という考えは正しいのですが、味付けに高カロリーなマヨネーズやドレッシングをかけ過ぎてしまうと本末転倒です
市販品のマヨネーズやドレッシングでは油分を調整することができませんので、サラダにかけるドレッシングは、体に良い油を使って手作りするのがおすすめです
そこで今回は、油の中でも体に良い影響を与えるとされる「オメガ3系の油」についてご紹介します。
油=脂肪になる・太る・体に悪い物だ と捉えている方もいるのではないでしょうか?
と捉えている方もいるのではないでしょうか?
しかし、油は肌や髪を美しく健康に保ったり、炎症を抑えたり、ホルモン類を生成する材料になったり、実は体にとって必要不可欠な物なのです。
油には様々な種類がありますが、どの油も適量を摂ることで、健康維持に効果を発揮します。
今回ご紹介するオメガ3系とは、油の種類の名称で、化学構造の違いから「オメガ3」「オメガ6」「オメガ9」と3種に分類されます。
上記の画像は、手前がオリーブオイル、奥が亜麻仁油(あまにゆ)です。
何年も前から健康に良いと注目されているオリーブオイルは、オメガ9系に分類されます。
キャノーラ油と同じ、オレイン酸を多く含む物がオメガ9系です。
加熱しても比較的酸化しにくいので、炒め物など加熱する料理におすすめの油です。
一方亜麻仁油はえごま油と同じく、最近注目が高まっているαリノレン酸を多く含む物で、オメガ3系に分類されます。
αリノレン酸は体内で合成されない必須脂肪酸であるため、食事から積極的に摂りたい油です。
オメガ3系の油は熱に弱いので、そのままかける、ドレッシングなどの加熱しない料理におすすめの油です。
体内で合成されないという点では、リノール酸を多く含むオメガ6系の油(べにばな油、ゴマ油、サラダ油など)も同じですが、現代人の食事にはこれらの油が多量に含まれていることが多いため、逆に摂り過ぎに注意したい油とされています。
近年、日本人の食事が欧米化したことにより、それまで自然に摂取できていたオメガ3系の油が不足した反面、オメガ6系の油を過剰に摂取しているという側面があり、油が体に及ぼす影響が見直されているのです。
オメガ3系の油は、血液をサラサラにし、動脈硬化、心筋梗塞、脂肪肝、高血圧などの生活習慣病を予防する効果が期待できるとされています。
また、代謝を促し脂肪の燃焼を促進させる効果や、脳を活性化させる効果も認められ、ダイエットや認知症の予防にもなると期待されています。
だからといって、オメガ3系の油だけを過剰摂取するのは逆効果で、冒頭に記述した通り、どの油も適量を摂ることが大切です。
例えば、血液をサラサラにする作用があるオメガ3系の油ですが、血液がサラサラで固まりにくくなると、出血をした場合に血が止まりにくいといった弊害が出ます。
オメガ3系の油はオメガ6系とは対極の性質を持つため、どちらもバランス良く摂取することで健康維持へと繋がるのです
また、油そのものを摂取しなくても、オメガ3系の油は、EPAやDHAが豊富な青魚やアーモンド、くるみなどのナッツ類、ほうれん草などの緑黄色野菜にも含まれています。
そのため、これらの食品を意識して食べるのも良いでしょう
ちなみに「えごま油」は「ゴマ油」と名前が似ていますが、原料は「えごま」というシソ科の植物の種子です
食品売り場などで見かける「しそ油」の原料も実は「えごま」で、「しそ油」と「えごま油」は商品名が違うだけで全く同じ物です。
お買い求めの際はご注意下さい
オメガ3系の油は熱に弱く、保存状態が悪いとすぐに酸化してしまいます。
開封したら冷蔵庫に保存し、2ヵ月以内には使い切るようにして下さいね。
さて今回は、アボカドと生ハムを使った「生ハムの洋風冷奴」をご紹介します。
白いお豆腐の上に載せたアボカドの緑と、生ハムのピンクがかわいい一品です。
生食用のオイルをかけて頂く、おしゃれなオードブル仕立てにしました。
おもてなし料理の一品に加えるのも、おすすめです
ぜひお試し下さい