2020年2月の記事
こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です

近年韓国の台所は、日本と同様に電力化が進み、ますます便利になっています。
とは言え、冬の寒さが厳しい韓国では、「温突(オンドル)」と言う床暖房施設が5世紀頃の三国時代からあったため、昔の台所事情が日本とは異なりました

今回は、「韓国における台所の変遷」について、各時代ごとにご紹介したいと思います


 三国時代
三国時代温突のある台所は、土間が他の部屋よりも一段低い場所にあります

と言うのも、温突は、薪や藁をくべて煮炊きしたときに発生した煙を、床下の煙道に通すことで床が温まる仕組みと、煙道が「¬」の字形で、家の片隅にある仕組みであるため、台所は温突と切り離せないからです。
そのため、冬は暖房代わりとして、調理をしないときでも火を焚き、床下は板石で土台を築き、きちんと火災予防の対策も取られていました。
ちなみに、韓国では台所のことを「釜屋(プオク)」と言います。
 高麗時代
高麗時代三国時代に貴族の家庭だけで使用されていた温突は、この頃には庶民にも普及されます

 朝鮮時代
朝鮮時代釜屋が家の中心に置かれ、各部屋に煙道が通るようになります。
食器棚には食器や燃料を置いたり、水瓶を備え付けて水を保管したりするため、中二階を作る場合も多くありました

釜屋の釜台は、「飯釜」や「汁釜」など、2〜3つに分けられた大釜が設置され、その大釜は鉄製で熱伝導が遅い一方、一度熱くなると冷めにくいため、重宝されます

また、大釜でご飯を炊くときは、米の中心に味付けした卵液をいれた容器を置き、ご飯と一緒に茶碗蒸しを作るといった工夫がなされていました

さらに、大釜の蓋は、持ち手を下に向けて、魚やチヂミを焼くフライパンとしても使用されたそうです

ちなみに、貴族階級の家には、台所の横にチャンバンと言う納戸を設置し、祭器などを保管しました。
 現代
現代温突は、台所機能がなくなり、床暖房だけが受け継がれていますが、床暖房は温水を循環させる仕組みへと変わりました。
日本も昔は土間の台所でしたが、暖房設備は囲炉裏やコタツですよね

それぞれの文化の違いは、知れば知るほどおもしろいです

さて、本日のレシピは、大釜の蓋で焼くチヂミ「レンコン海鮮チヂミ」をご紹介致します

通常は酢醤油で頂くのですが、知り合いの韓国料理店のシェフから、塩で食べるチヂミを教えて頂きましたので、今回採用しました。
皆さんも、ぜひお試し下さい



こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です

今年は、新型コロナウィルス感染症「COVID-19」の世界的な流行がみられ、心配な日々が続いていますね。
1日も早い終息を願います。
職業柄、栄養や健康に関する相談をされることが多いのですが、今年のように感染症が流行すると決まって「何を食べれば病気を防ぐことができますか?」と聞かれます

まずは、日々の食事でバランス良く栄養を摂り、腸内環境を整え、免疫力を上げておくことが重要です。
ただし、流行がはじまってから、急に何かひとつの食品をたくさん食べても、感染症を防ぐ効果は低いと考えます。
昨今、テレビやインターネットなど、様々な媒体から情報が流れてきますが、なかには間違った情報や、誇張された情報も多く含まれています

そのため、情報をしっかりと精査し、人ごみを避けて、手洗い、うがいをしっかりと行ない、バランスの良い食事と睡眠をしっかり取ることが感染予防には大切です。
感染症予防の基本を踏まえたうえで、管理栄養士としてオススメしたい食材は、「旬の食材」

旬の食材は栄養価が高く、身体のバランスを整える効果が期待できるので、旬の食材を食卓に取り入れることは、身体を健やかに保つうえで大切なポイントとなるでしょう


 「かんきつ類」の栄養価の高さは果物のなかでもトップクラス
「かんきつ類」の栄養価の高さは果物のなかでもトップクラス
カロテンよりも抗酸化作用が高い、βクリプトキサンチンを多く含むことが注目されており、ビタミンCとの相乗効果で感染症予防や免疫力を高める効果が期待できます

また、白い薄皮には、毛細血管を強くし、動脈硬化の予防に効果が期待できるビタミンPが含まれているので、みかんなど、皮の薄い物は皮ごと召しあがるのがオススメですよ。
かんきつ類は、温州みかん、バレンシアオレンジ、せとか、ネーブルなどの「みかん、オレンジ類」と、グレープフルーツ、夏みかん、スウィーティー(オロブランコ)、メロゴールド、はっさく、伊予柑、バンペイユなどの「雑柑、グレープフルーツ類」に分けられます。
昨今では、ミカン×オレンジ=きよみ、文旦×グレープフルーツ=メロゴールド、スウィーティー(オロブランコ)など、様々なかんきつ類同士が掛け合わされ、新しい品種が生まれていますよ

 栄養価が高く、おいしいかんきつ類ですが、薬との飲み合わせには注意が必要です。
栄養価が高く、おいしいかんきつ類ですが、薬との飲み合わせには注意が必要です。一部のかんきつ類には、「身体のなかで薬を分解する酵素」の力を抑える成分が含まれているため、薬の分解がうまくいかず、身体に薬が蓄積し、副作用が出る恐れがあります。
例えば、高血圧の薬では、血圧が下がりすぎるために「めまい」や「ふらつき」などの、低血圧症状が現れる可能性があるのです

薬との飲み合わせに注意が必要なかんきつ類は、グレープフルーツ、文旦、はっさく、夏みかんなどがありますが、上記でご紹介したように、他にグレープフルーツと掛け合わせた品種もありますので注意が必要です。
また、グレープフルーツ果汁のジュースも避けるようにしましょう

一方で、バレンシアオレンジ、温州みかん、デコポン、伊予柑、ゆず、カボス、キンカン、すだちなどは薬に影響する成分をほとんど含まないため、召しあがって頂いても大丈夫です

薬との飲み合わせで迷われたときは、管理栄養士や薬剤師にご相談下さいね

さて、今回ご紹介する「オレンジとチキンのパエリア風」は、オレンジ風味のさわやかなパエリア風の炊き込みご飯です。
炊飯器で手軽に作れますのでぜひお試し下さい



こんにちは。野菜と豆腐の料理家あらため、豆腐料理研究家の江戸野陽子です
こちらで豆腐料理を紹介するようになってから、豆腐をメインに扱うようになりまして、肩書きを「豆腐」オンリーにすることにしました。
とは言え、活動内容は今までと変わりません。
どうぞよろしくお願いします
さて、今回は豆腐の発祥地について話したいと思います。 豆腐の起源は中国にあり
豆腐の起源は中国にあり
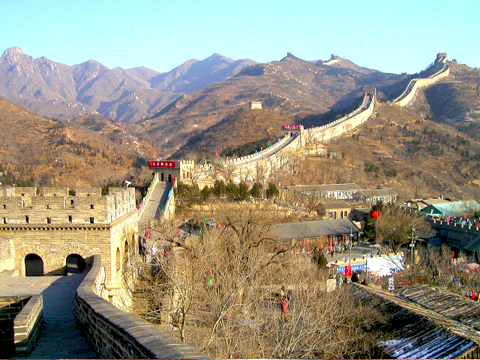
豆腐の起源にはいくつかの説があります。
そのなかで、有力と言われるものはふたつあります。 紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている
紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている
 豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。
豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。
このように豆腐は、少なくとも唐代中期頃に作られていたと言われているようです
 中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!
中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!

日本には木綿、絹ごし、おぼろ、充填豆腐など、色んな種類の豆腐がありますが、中国はそれ以上と言われています。 よく知られている豆腐は、以下のような物があります。
よく知られている豆腐は、以下のような物があります。 嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐
嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐 老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐
老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐 豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。
豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。 豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。
豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。 臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。
臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。 腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。
腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。
料理によく活用されているのが、老豆腐なのですが、これは日本の木綿豆腐より固くて水分が少なめなのが特徴です。
それもこれも、中国では豆腐を加熱調理(揚げる、焼く、煮る)することが多く、水分がない方が良いからなのだと思っております。
実際、本場中国の麻婆豆腐を食したことのある方々は、「麻婆豆腐の豆腐は、水分が抜けてスポンジに近い状態になっていて、そこに味が染み渡っていて、おいしいんだ」と、教えてくれます
 木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう
木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう

そこで今回は、水切りした木綿豆腐を使って作る「四川麻婆豆腐」をご紹介したいと思います
ポイントは、木綿豆腐をレンジで加熱してから水切りすること
鍋で沸かしたお湯でゆでるより、レンジの方がしっかりと水切りができるので、レンジをオススメしています。
木綿豆腐をキッチンペーパーで包んでから加熱し、重しを乗せて、しっかりと水切りしてあげて下さい。
こうすることで味が豆腐に絡みやすくなり、かつ崩れにくい四川麻婆豆腐が作れますので、ぜひお試し頂けたらと思います


こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです

メタボリックシンドローム、体脂肪、中性脂肪、BMIなど、身体の健康にかかわる言葉は皆さんご存じだと思います

体内脂肪に関係の深い用語ですね。
体内脂肪と聞くとあまり良いイメージはないかと思いますが、脂肪は栄養を蓄える貯蔵庫、体温保持、衝撃から身体を守るなど、身体にとってはなくてはならない物です。
しかし、増えすぎてしまうと、体形の問題以上に様々な病気の要因となってしまいます


 そもそも、何故、脂肪はついてしまうのでしょうか?
そもそも、何故、脂肪はついてしまうのでしょうか?
人は食事で得られる栄養をエネルギー源とし、身体を動かしていますが、筋肉や内臓が必要としている以上の栄養を摂ると、それらはいざというときに使うための体脂肪として蓄えられます
また、体脂肪を構成する脂肪細胞は、膨らんで大きくなると分裂をしますが、このサイクルが繰り返されることで、体脂肪はいくらでも増えてしまうのです
 体脂肪の主な原因は糖質や脂質の摂りすぎですが、今回は「脂質」についてお話していきたいと思います。
体脂肪の主な原因は糖質や脂質の摂りすぎですが、今回は「脂質」についてお話していきたいと思います。
脂質は、動物性脂肪と植物性脂肪のふたつに代別されます。
「どちらが健康に良いのか?」と言う二極論になりがちですが、ポイントは油を構成する脂肪酸。
動物性脂肪は、バター、ラード、肉の脂身に代表され、「飽和脂肪酸」と呼ばれています。
一方で植物性脂肪は、オリーブ油、サラダ油、魚油などがあり、「不飽和脂肪酸」と呼ばれています。
どちらも最終的には体脂肪となるため、バランス良く摂取することが基本です
 さて、そのなかで「必須脂肪酸」と言って、私たちの身体では合成することができない油をご存知でしょうか
さて、そのなかで「必須脂肪酸」と言って、私たちの身体では合成することができない油をご存知でしょうか
必須脂肪酸には、オメガ6系脂肪酸(リノール酸 ごま油、紅花油など)と、オメガ3系脂肪酸(α-リノレン酸、えごま油、亜麻仁油、EPA、DHA)の2種類がありますが、近年オメガ6脂肪酸の摂りすぎが問題となっており、オメガ6脂肪酸を減らし、オメガ3脂肪酸を摂ることが推奨されているのです
オメガ3系脂肪酸は酸化されやすいので、生食が適していますよ
オメガ9系脂肪酸(オレイン酸)にはオリーブオイルがあります。
こちらは体内でも合成が可能な脂質ですが、悪玉コレステロールの濃度を減らす働きがあるので、しばしば身体に良い油と取り上げられていますね。
店頭には、様々な種類のオリーブオイルが並んでいて値段もまちまちですが、大きく分けると、エキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルがあります。
エキストラバージンオリーブオイルは、オリーブの実の生絞りですので、そのまま生使いが風味を味わう上ではおいしい食べ方です
一方のピュアオリーブオイルは、精製過程でポリフェノールなどが取り除かれているので、風味は劣りますが、酸化しづらくなっているので、炒め物、揚げ物など、火を使う料理に使えます
脂質の特性を知って、上手に使い分けると、おいしさはもとより、健康効果がさらににアップしますよ
さて、本日のレシピは、ヘルシーでお腹満足の食べるサラダ、「ナッツのホットサラダ」をご紹介致します
皆さんも、ぜひお試し下さい





























