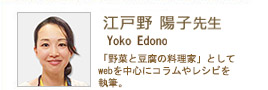江戸野 陽子先生のブログ
こんにちは
野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。
今回は、出汁の旨みをおからに吸わせ、具材と一緒に炊いて作る、「卯の花」を作ってみようと思います。
旨みをたっぷりと含んだおからと、具材が渾然一体になって、なんとも優しい味です。白いご飯がいくらでも進みますよ

さて、卯の花作りで最初にぶつかる壁が、「具材選び」と「炊き方」。
それぞれについて解説してみたいと思います。 具材選び
具材選び
カレーならジャガイモやニンジン、タマネギ、肉じゃがならジャガイモ、肉、白滝と誰もが口を揃えて答えますが、卯の花には共通の定番具材がある訳ではありません。
そうすると、何を選ぶかは料理する人の好みとセンス次第になるのですが、これは正直恐ろしい
適当に選んで、おいしくない卯の花になってしまったら残念ですよね。
そこで、個人的に考えた指標をお伝えします
おいしい卯の花を作るには、「彩りの良い素材」、「歯ごたえの良い素材」、「風味の良い素材」の3つを選びましょう。
彩り要員としては、ニンジン、枝豆、ひじきなど、出汁としょうゆで煮ても茶色く染まらない物があると良いです。
歯ごたえ要員には、ゴボウ、レンコン、大豆、こんにゃくなど。
そして風味要員には、干しシイタケ、青ネギなど香りや旨みの強い物を。
この3つにプラスアルファで、お好みの具材を入れると良いと思います。
プラスアルファするなら、油揚げ、鶏肉、タケノコ、昆布、ちくわ、かまぼこ、卵など、個性のある物や季節に合わせた物を選ぶと良いでしょう。
ちなみに、私の実家では、細切りにしたなるとを入れていたのですが、白とピンクの色味と、やわらかな弾力が卯の花にアクセントを加えていました。 炊き方
炊き方
おから自身がすでに加熱済みなので、どれくらい出汁を足せば良いのか、分かりにくいようです。
実際私も、大量の出汁で炊いてべちょべちょの仕上がりになってしまったり、少なめの出汁にして味が染みこまずにパサパサの仕上がりにしてしまったりしました
そこで、おいしく炊くためのポイントをふたつお教えします
 おからの水分を乾煎りして飛ばす。
おからの水分を乾煎りして飛ばす。
おからは、店舗によって水分量が異なるので、まずはフライパンで乾煎りして水分を飛ばします
これは、おからに味を染込ませやすくなるというメリットもあるので、しっとりしているおからが、パラリとするくらいまで中火で乾煎りしましょう。
もちろん電子レンジで加熱してもOK。 出汁はおからの分量の1.6倍(あくまで目安なので参考数値にして下さい。)
出汁はおからの分量の1.6倍(あくまで目安なので参考数値にして下さい。)
これ以上だと多いし、少ないとおからが出汁を吸った塊のようになってしまいます。
そうして、調味料と一緒に中火で6〜8分くらいかけて炊きましょう。
しっとりと仕上がれば、大成功です
さて、本日は、根菜のシャキシャキ感と、干しシイタケのしっとりとした甘みがたまらない一品、「五目卯の花」をご紹介致します
今回は、ニンジン、干しシイタケ、枝豆、こんにゃく、レンコンで作っています。
皆さんも、ぜひお試し下さい