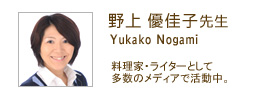こんにちは。料理家の野上優佳子です
我が家の3番目は、末っ子長男。
これまでは、娘たちの雛祭りが子どもの祝いでしたが、長男誕生をきっかけに、端午の節句もお祝いするようになりました
さてこの端午の節句、どんな意味かと言いますと…。
端午の「端」ははしっこ、ものの初め、という意味で、つまり月のはじめの午の日を指し、午の音の響きから「五」に通じたことと「重日思想」の影響で、5月5日になったと言われています。
ちなみに「重日思想」とは中国の古い思想で、月と日の数が同じ数字となる日付(重日)は、めでたい特別な日である、というもの。
日本の祝日などに重日が多いのは、この影響なのですね。
さて、この端午の節句につきものなのが、菖蒲(しょうぶ)と鯉のぼり。
菖蒲は、その香りの高さが邪気を払うと言われます。
菖蒲湯としてお風呂に入るのが一般的ですが、軒先に飾ったり、髪にさしたり、枕に入れたり、という風習もありました。
武道を重んじるという意味の「尚武」と同じ響きであることや、葉の形が刀に似ていることも、男子の節句にぴったりだったのでしょう。
鯉のぼりは、滝を登りきって竜になる鯉の故事から、立身出世のシンボルである鯉が掲げられるようになったそうです

また、端午の節句には粽(ちまき)や柏餅をいただく風習があります。
粽は、茅(ちがや)の葉で米を巻いたことが名前の由来と言われ、日本でも平安時代にはすでに文献に登場します。
古く「楚」の国政を預かった「屈原」という偉大な詩人が、謀略に陥れられた末に川に身投げしたのが5月5日。
その屈原の霊を慰めるため命日に米を入れた竹筒を投げ入れる風習が、粽の始まりだと言われています。
一方、柏餅の歴史は比較的新しく、一説によると江戸中期頃につくられたもの、とのこと。
柏の木は、新しい芽が出てこないうちは古い葉が落ちないことから、家系が絶えることなく繁栄する、子孫繁栄への縁起かつぎの意味があります。
行事食には、ちゃんと意味があるのですね。知れば知るほど、興味深い世界です。
今回は、子の未来の幸せを願う祝いの日におススメの、子どもも食べやすく、しかも見た目がとても楽しいお寿司をご紹介
グラスを使って、まるでカップケーキのように盛り付けします。ぜひお試しを