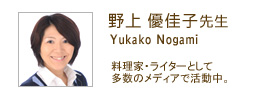こんにちは、料理家の野上優佳子です。
日本には季節を表す美しい言葉が数多くあります。
雑節(季節の変わる様子を示す特別な暦日)の「入梅」もそのひとつ。 梅雨の始まり を告げるこの呼び名は、梅の実が熟してくる頃であることが由来とされます。
梅雨の始まり を告げるこの呼び名は、梅の実が熟してくる頃であることが由来とされます。
その定義は様々ですが、芒種の後の最初の壬の日がその日に当たるとされるのが一般的で、6月11日頃を指します。
ちなみに芒種(ぼうしゅ)とは、二十四節気のひとつで、稲や麦など穂の実る植物の種を蒔く頃という意味です
豊かな実りを予感させる、とてもステキな言葉ですね

さて、季節の名前になる程私たちになじみ深い梅
バラ科サクラ属の落葉高木で、春告草という別名を持つように可憐な花を咲かせて初春の到来を知らせてくれます。
今は青々とした実を付けはじめ、熟れるにしたがって黄色くなります。
食用としての梅の歴史はとても古く、もともとが観賞用でなく薬用と調理用に輸入された背景があります。
平安時代には解熱剤や消炎剤、整腸剤など幅広く薬用とされ、梅の実から作る梅酢がごく一般的な調味料として使われていたことが当時の医学書や有職故実にも記されています。  未熟な青梅の種子は毒性があることが分かっているので、生でかじりつくのは避けて下さいね。
未熟な青梅の種子は毒性があることが分かっているので、生でかじりつくのは避けて下さいね。
(梅酒や梅干しなどに漬けた場合は、アルコールや塩分などで酵素が不活性化しているので問題ないそうです)
普段何気なく使っている季節の言葉には、日本人の暮らしの知恵がひそんでいます。
それをちょっと知るだけで、改めて季節を楽しむことができますね
さて今回は、そんな入梅におススメの1品。
イワシをお酢で煮たさっぱりお総菜「イワシの酢煮」をご紹介します。
体を元気にしてくれる お酢の効果で骨までやわらかく煮るので、
お酢の効果で骨までやわらかく煮るので、
丸ごと食べられて栄養満点
ぜひお試し下さい。