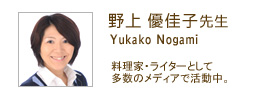こんにちは、料理家の野上優佳子です。
みなさま、ポートランドという場所をご存知でしょうか?
全米の住みたい街人気ランキングでトップクラスに入り、また屈指のグルメシティとして名高いオレゴン州の都市です
個人的には、仲の良い友人が現地で食にかかわる仕事をしていることもあり、とても興味がある街でもあります。
また日本からもビジネス目的で視察に訪れる人が年々増え続けているそうで、日本国内からの注目度も高い都市のひとつなのです
先日、そんなポートランドからのゲストを迎えた、街づくりに関するトークセッションが横浜で開催されました
友人がゲストスピーカーだったこともあり足を運んだのですが、非常に興味深い話を聞くことができました
特に印象深かったのが、食と街とのサスティナブル(sustainable/持続可能)な関係性についてです。
食に限らずですが、ポートランドでは下記のような価値観が根付いています。 環境に配慮した暮らし方を目指し、マスプロダクト(mass+products/量産品)よりもハンドメイド(handmade/手製)を選び、地域で丁寧に作られた食物を地域で消費する。
環境に配慮した暮らし方を目指し、マスプロダクト(mass+products/量産品)よりもハンドメイド(handmade/手製)を選び、地域で丁寧に作られた食物を地域で消費する。 むやみに生産量を増やさず、むやみに低価格を求めず、儲け主義に走りすぎない。
むやみに生産量を増やさず、むやみに低価格を求めず、儲け主義に走りすぎない。 ローカル・ファースト(地元第一主義)がしっかりと根付き、生活の一部として生きている。
ローカル・ファースト(地元第一主義)がしっかりと根付き、生活の一部として生きている。
そこには生産者と消費者(そしてその間を取り持つ商業)が、足並みを揃えないと実現しない町作りがありました。

日本にもポートランドの価値観に似たものがあり、「身土不二(しんどふじ)」といった言葉もあるのです。
これは明治時代の医師であり陸軍軍医だった石塚佐玄氏によって提唱された食養運動のスローガンで、住んでいるその土地、その環境に適している食物(旬の物、郷土の料理)を食べることが心身を健やかにするという考え方です。
また、1980年代の初めには「地産地消(ちさんちしょう)」という言葉も生まれました。
地産地消とは、地域生産・地域消費の略語で、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供される物に限る)を、その生産された地域内において消費する取り組みです。(農林水産省ホームページより引用)
元々は農林水産省の、地域内において食生活を向上させる対策事業計画案の中で生まれた言葉だと言われています。
現在では、一般名詞として普及する程になりました。
現在の日本では、地産地消に取り組みたいと思っていても、輸入に頼っている食材があることや、農業生産者が少ない地域があることなどの理由から、実現には多くの困難があり、なかなか行動に移せないのが現状です。
現在のポートランドの姿は、そんな現代の日本が理想として描き続けているものを具現化した、ひとつの理想だとも言えるのではないでしょうか。
そのことが、日本人の多くを惹き付けている所以(ゆえん)なのかも知れませんね。
私たちはどんなふうに自分たちの食を守り、支えて行けば良いのでしょう……。
ポートランドの友人からお土産にもらった、とびきり新鮮なポートランド産のオリーブオイルと、ポートランドの農業を牽引する農場で作られた美しいカリンのジャムに舌鼓を打ちながら、改めてそんなことを考えさせられました
さて今回は、夏野菜をたっぷり頂ける「チキンと夏野菜のオイル煮」をご紹介します。
オイル煮は日持ちするので、作り置きにもおすすめ
そろそろ夏野菜をスーパーで見かける時期ですので、地産地消ということでレシピ内の食材を地元で採れた野菜に変えてもOKです
また冷蔵庫に中途半端に残っている野菜を、あれこれ入れてみても良いですよ
いつもの野菜をごちそうに変えてくれるお料理ですので、ぜひ作ってみて下さいね