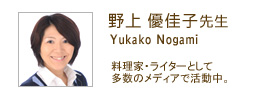こんにちは、料理家の野上優佳子です。
1月も残りわずか、まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではもうすぐ立春 です。
です。
立春とは、四季を細かく分けた二十四節気のひとつで、今年は2月4日が立春の日に当たります。
立春の前日は「節分」と呼ばれ、文字通り「季節を分ける」という意味です。
現代で「節分」と言えば2月3日頃(年によって2日や4日のこともあります)が一番有名で、「豆まきをする日」や、「恵方巻きを食べる日」だと連想する人も多いかと思います。
しかし本来は、「節分」とは立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれ前日を指します
なぜ「立春」の前日の「節分」だけが季節の行事として浸透しているかというと、明治時代より以前の「旧暦」が使われていた頃、一年の始まりは立春からと考えられていたためです
冬から春に変わるこの節目はとても重要とされ、立春が一年の始まりとすれば、前日の「節分」は現代の「大晦日」に当たります。
そこで、一年間の厄払いをする意味を込めて「節分」に「豆まき」が行なわれました
「豆」=「魔滅(まめ/魔を滅する)」に通じ、無病息災を祈る意味があることや、鬼が出たとき、毘沙門天のお告げにしたがって大豆を鬼の目に投げ付けて退治した伝説がもとになっています。

皆さんは、どんな「節分」を過ごしますか?
掛け声とともに家の中に豆をまくのが一般的ですが、豆を囲炉裏の縁に火を囲むように12個並べ、それを各月に見立てて、焼け具合から天候や豊凶を占う地域もあるそうです
我が家では毎年、イワシの頭 を柊や豆殻に刺して玄関の戸口
を柊や豆殻に刺して玄関の戸口 に飾ります。
に飾ります。
これはイワシの臭気や柊の棘で、鬼を家に近づけさせないおまじないです。
地域によっては、イワシの他に、ネギやニンニクを焼いた物を刺すところもあるそうです。
ネギもニンニクも臭いは強烈ですから、効き目がありそう
とは言え、香味野菜を焼いた香りは、私は逆に食欲がそそわれる気がしますが、西洋のドラキュラもニンニクが苦手とされていますから、鬼やドラキュラはずいぶん繊細で鼻が利くのですね。
さて、豆まきをしたあとは、豆を年の数だけ食べる風習もあります。
年を重ねるにつれて食べる豆の量が増え、少し辛く感じることも…
煎り豆を一袋買って、家族みんなで食べるものの、すぐに食べ飽きて残すことがありませんか?
そんなときは、甘いおやつにアレンジするのがおすすめです
そこで今回は、「煎り大豆のキャラメリゼ」をご紹介します。
煎り大豆に黒砂糖を溶かして飴状にした物を絡め、カリッとした食感の甘いお菓子。
我が家では、お茶 請けに出すと、あっという間に食べ切ってしまう人気メニューです。
請けに出すと、あっという間に食べ切ってしまう人気メニューです。
材料は豆と砂糖と水、使用する調理器具もフライパンひとつで手軽にできますよ
ぜひお試し下さいね