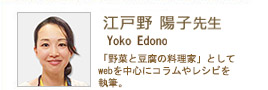江戸野 陽子先生のブログ
2020/07/22
こんにちは!
野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です

今回は「油揚げの種類と選び方」についてお話したいと思います。
と言うのも、ひと口に油揚げと言っても、薄い物や厚い物があるので、ぜひともその使い分けについて知って頂きたいからです。
東京育ちの私にとって、油揚げと言ったら薄くて卵色をした油揚。
それを刻んで味噌汁に入れたり、煮物にしたり、いなり寿司にしたりしていました。
しかし、全国に目を向けると本当に色んな油揚げがあるのです

例えば座布団のように分厚い油揚げがあります。
これをおでんにしたり、カリッと焼いてしょうゆと薬味で頂いたりする地域もあります。
そこで、より油揚げのことを知って頂きたいので、油揚げの種類を解説したいと思います

ここでは大きく3つに分類し、それぞれの特徴を紹介します

 薄揚げ
薄揚げ
薄揚げは厚さが1cm前後ほどの油揚げで、やわらかく、色も白めで、しっとりとしているのが特徴。
形は長方形の物が多く、「油揚げ」、「うすあげ」、「京あげ」などの名称で陳列されています。
京都で食べられていた「うすあげ」「京あげ」は、皮のように薄く、しっとり感が高くてしなやか

生地に水分が含まれており、口に含んだときにジュワッとした物を感じられ、断面が非常にきめ細かいです。
ちなみに同じ薄い油揚げでも、水分が少なめで生地をカリッと揚げたタイプもあります。
こちらは非常に軽くて、しっとり感がない代わりにカラッとしており、油っぽさが控えめで、油抜きが不要になっていることが多いです。
長方形の物が主流ですが、正方形でいなり寿司用の「すしあげ」として売られている物もあり、油抜きの作業を省くことができるので大変便利です。
いなり寿司やきつねうどんのお揚げなど、薄揚げじゃないと作れない物があるので、こちらの情報を参考に選んでみて下さい

 メインを張れる厚くて大きな大判油揚げ
メインを張れる厚くて大きな大判油揚げ
次に紹介するのが大判油揚げ。
こちらは、各地それぞれで独自の文化をひっそりと形成してきたので、その地域でしか知られていない物が非常に多く、手に入りにくい物もあります。
大判油揚げは、厚揚げみたいに分厚くて、大きいのが特徴です。
薄皮がパリッとしており、中はみっちりとした肉厚感があり、水気は多めでしっとりとしている傾向にあります。
東北地方だと三角形の肉厚油揚げ、北陸地方だと座布団みたいに分厚い物、中国、四国地方だと正方形の肉厚な物などがあります。
焼いて薬味を乗せたり、鍋に加えてスープを吸わせるだけでも、メインになれるような油揚げです。
町の豆腐屋さんには、その日揚げた一番おいしい物があるので、機会があればぜひ食べて頂きたいと思います

 パリパリの日持ちタイプ
パリパリの日持ちタイプ
こちらは豆腐生地を十分に脱水させ、芯までカリカリに揚げたタイプで、板のようになっています。
特筆すべきは消費期限で、水分を飛ばしてカリカリに揚げているため、3ヵ月以上保存が可能。
有名な物に「松前あげ」や「南関あげ」があります。
水や出汁に浸すと、他の油揚げにはないもっちりとした食感になるのが特徴で、長持ちするので常備しておくと大変便利です

油揚げの種類がいろいろあることを分かって頂けたでしょうか。
料理に合わせて、油揚げを選べると、いつもの料理がレベルアップすると思いますので、覚えて頂けたら嬉しいです

さて、今回は京揚げに具(挽き肉、オクラ、ニンジン)を巻いて作る一品、「油揚げロール」をご紹介致します

京揚げの薄くてしっとりとした食感を活かして作る、ボリュームたっぷりの一品です。
出汁を吸った油揚げのジュワジュワとした食感で、お肉がよりジューシーになりますよ。
油揚げは、一度下ゆですることで、余計な油が抜けて味が染みやすくなるので、このひと手間は大切です。
皆さんも、ぜひお試し下さい