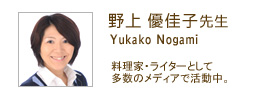こんにちは、料理家の野上優佳子です。
いよいよ今年も間もなく終わりとなります。
大掃除やら忘年会やらで、皆さん目まぐるしい毎日ではないでしょうか。
皆さんは大晦日(おおみそか)にはどんなふうに過ごしますか?
必ず食べる物はありますでしょうか?
一般的に大晦日に食べられる物となると、やはり年越しそばかと思います
年越しそばの由来は、実に様々です。
例えば「細く長く幸せをそばからかきこむ」といった謂(いわ)れや、「そばは切れやすいから1年の災厄を断ち切る ために食べる」といった謂れがあります。
ために食べる」といった謂れがあります。
またその他にも、「そばは金を集める縁起食材」であるという謂れがあります。
この「そばは金 を集める」といった謂れは、元々は江戸の金細工師が仕事納めにそばがき(そば粉を練っただんごのような物)で畳の目に詰まった金粉
を集める」といった謂れは、元々は江戸の金細工師が仕事納めにそばがき(そば粉を練っただんごのような物)で畳の目に詰まった金粉 をくっつけて取ったことから由来しているそうです
をくっつけて取ったことから由来しているそうです
また、そばにはつきものである薬味のネギですが、実はこれも縁起物です。
ネギ→労ぐ(ねぐ)に通ずると言われており、労ぐとは古語で「心を和らげる」という意味になります。
そこから年越しそばと共にネギを食べることで、「1年の穢れを落とし、心安らかに新年を迎える」と言われているのです。
ちなみにこの労ぐという言葉は、神社の宮司の補佐役である役職「禰宜(ねぎ)」の由来ともなっているのだとか。
ネギには薬味という味覚としての役割はもちろん、実は縁起的な意味も紐付いているのです。

もうひとつ、大晦日の食べ物をご紹介しましょう
東北地方を中心に今でも残る風習で、「年取り膳(としとりぜん)」というものもあるのをご存知でしょうか?
これは大晦日に食べる夕方膳を言い、1年の無事を感謝し新しい年神様を迎えるための祝いの食事を、1人ずつのお膳にして食べる風習のことです。
地域によってお膳の献立の違いはありますが、お膳のひとつに魚を食べる地域がとても多く、そのときに食べる魚を「年取り魚 (としとりざかな)」と呼びます。
(としとりざかな)」と呼びます。
東北の一部では真鱈を、東日本全域は塩鮭、静岡などではカツオ、西日本はブリ、その他では尾頭付き鯛を食べる地域もあります。
地域ごとに違う魚が年取り魚として食べられているだなんて、とても不思議ですね
今年は心機一転、お住いの地域以外で食べられる年取り魚を食べてみてはいかがでしょうか
いつもとは少し違ったお正月を迎えられるかもしれませんよ
さて今回は、おせちのメニューや年取り膳にも使える「サケの粕漬け」をご紹介します。
粕床作りはとても簡単
一度覚えたら、鱈やサワラなどの魚類だけでなく、お肉にも活用できます。
ぜひお試し下さいね