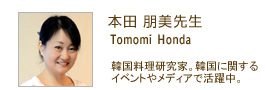こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
先月、ソウルで韓国のデザート「後食(フシク)」について勉強してきました
後食とは、韓国語で「デザート」を指す言葉です。
その中でも、韓国独自の伝統的なお菓子を総称して「韓菓(ハングァ)」と呼びます。
韓菓の歴史は古く、13世紀末に刊行された史書「三国遺事」に高麗時代の宮中儀式で使われた記述があります。
その背景には、高麗時代に仏教文化の影響を受け、緑茶が飲まれるようになったことがあります。
茶の隆盛に伴い、菓子類も発達したようです。
その後の朝鮮時代には嗜好品として、韓菓は王家の婚礼儀式や客のもてなしに欠かせない物となり、様々な種類が作られるようになったと言われています。
そして近代に入ると、庶民の間でも韓菓が広く作られるようになります。
現代の韓菓は、祭祀やお祝いのときに出されたり、贈答品として用いられたりする他、日常的におやつとして食べられるようになりました。
韓菓は主に、もち米粉、小麦粉、片栗粉などの穀物の粉や、くるみ、なつめ、松の実などの堅果類、果物などを材料に作られる菓子で、素材の味を活かした優しい味わいの物が多いです。
韓菓の種類は数百種あるとも言われていますが、中でも代表的な物を挙げてみましょう
 薬菓(ヤックァ)
薬菓(ヤックァ)
小麦粉にハチミツ、ゴマ油、シナモンパウダー、ショウガ汁などを混ぜ合わせてひとつにまとめてから、生地をのばし型抜きで抜き、低温で揚げてシロップに絡めた物です。 油菓(ユグァ)
油菓(ユグァ)
もち米粉で作った生地を蒸してから、食べやすい大きさに切り乾燥させ、油で揚げてゴマや粉類をまぶした物で、サクサクとした食感があとを引きます。
10日間程水に漬けて発酵させたもち米粉を使うなど、時間も手間もかかるお菓子なので、古くは新婦から新郎家族への心を込めた贈り物として使われていました。 強精(カンジョン)
強精(カンジョン)
松の実やゴマ、豆類などをシロップに混ぜてから煮つめた物を、木枠に入れて成形し、固まったあとに食べやすい大きさに切り分ける、シリアルバーのようなお菓子です。 正菓(チョングァ)
正菓(チョングァ)
根菜類などの野菜や果物を一度湯がいたあとにじっくりと砂糖で煮つめた物です。
正菓には二種類あり、じっくりと煮つめる工程で完成の物と、その後乾燥させる物があります。
昔はそのままで食べていましたが、近年は餅のトッピングとしても使われています。 茶食(タシク)
茶食(タシク)
片栗粉やきな粉などの粉にはちみつを混ぜて練り、専用の木枠で型抜きしたお茶菓子です。
伝統的な韓菓は日本でほとんど知られていませんが、どれも素朴な味わいで、一度食べるとクセになるおいしさです。
韓国のデパートや専門店などで手に入りますので、旅行に出かけたときはぜひ食べてみて下さいね
さて今回は、韓菓の中から、比較的簡単に作れる「梅雀菓(メジャックァ)」をご紹介します。
上記では挙げませんでしたが、これも韓菓の代表的な物です。
名前の由来は、「梅に雀が座ったような」特徴的な形にあります。
上品な甘味のシロップと、カラッと揚がった生地の食感がやみつきになる一品ですので、ぜひお試し下さい!