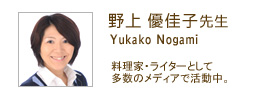こんにちは、料理家の野上優佳子です。
先日、今や世界共通語になりつつあるbento(弁当)がご縁で、ポルトガルのお弁当箱メーカーのデザイナーと友人になりました
きっかけは、最初に一緒に仕事をしたときのことです。
デザイナーである彼女自身が子育てをする中で、「スクールランチだって1日の食事のひとつだから、ヘルシーでおいしくて楽しい物が良い」という考えのもとにプロダクト(product/製品)を作っているという話になりました
その考えに共感した私と彼女はすっかり意気投合し、改めて一緒に仕事をすることになったのです

食というのは人間を形作る上で大切なことです。
そのため、「食」に関する話題は初対面同士でも盛り上がれる、数少ないコンテンツのひとつではないかと私は思っています。
初対面の私たちが盛り上がったのも、弁当の話を含めた「食」についてでした
その中で面白かったのは、「日本とポルトガルは、食の嗜好性が近い」ことに気付いたことです
ポルトガルの人々は、よく米を食べます。
そしてポルトガルは肉や野菜はもちろん、日本と同じく魚介類もよく食べる習慣があります。
イワシやタコ、イカ、エビなど
私たちにも馴染みのある魚介類が、ポルトガルでも一般的に食べられているのだそうです。
その中でも「バカリャウ」という塩漬けの干しタラは、ポルトガル料理になくてはならない物だとか。
ちなみにバカリャウは他の国でも食べられており、スペインでは「バカラオ」、イタリアでは「バッカラ」と呼ばれています。

ポルトガルでバカリャウがどんな風に食べられているのかというと、出汁に使ったり、戻した身をほぐしてコロッケにしたり、グラタンに入れたり、炒めたり、卵とじにしたりと、とにかくメニューが豊富なのです。
私の故郷である青森でも、津軽生まれの祖母が作る煮しめの具と出汁には、「棒鱈」(ぼうだら)と呼ばれる干しタラが欠かせない食材でした。
そのためか、なおさらポルトガルに親近感を覚えるのかもしれません
日本とポルトガルの国交の歴史は、1543年に種子島へポルトガル商人が漂着したことが始まりです
鉄砲伝来として、日本史の中でも有名な史実ですね。
ヨーロッパ各国の中でもオランダと並びもっとも長い友好の歴史があると言われており、2010年には修好通商条約締結から150年を迎えました。
ポルトガル料理は本当に、私たち日本人が初めて食べても、なんだか懐かしささえ覚えるような、そんな親しみある料理が多いです。
なにせ、代表的な日本食とされている天ぷらの起源はポルトガル料理ですし、その他にもビスケットやカステラ、金平糖(ポルトガル語でcofeito/コンフェイト。球状の砂糖菓子の意味)などは、もともとはポルトガルのお菓子です。
私たちに馴染みのある物で、実はポルトガルから渡来し、名前にもその音の由来を残しながら日本で成熟した物は結構多くあるのですよ。
そう思うと、遠い国がなんだかグッと近くに感じますね

さて今回は、ポルトガルで定番の米料理「ピーマンのピラフ」をご紹介します
ポルトガルでは、肉や魚料理の付け合わせとしてピーマンのピラフを食べます。
日本人の舌にも合うおいしさなので、新たなピーマン料理のレパートリーになること間違いなしです
ぜひお試し下さい