2017年4月の記事
 料理家の野上優佳子です。
料理家の野上優佳子です。昨年、日本の研究チームが、「キヌア」のゲノム(遺伝情報の総体)配列の解読に世界で初めて成功した」というニュースが飛び込んで来ました

皆さんは、この「キヌア」というスーパーフードをご存知でしょうか

スーパーフードとは、栄養バランスに優れ、栄養価の高い食品のこと。
料理の食材としての用途と、健康食品としての用途を併せ持つ、食品とサプリメントの中間のような存在です。
 キヌアの原産地は、南米アンデス山脈。
キヌアの原産地は、南米アンデス山脈。干ばつや塩害などの厳しい環境下でも栽培できる作物として、15世紀のインカ文明が栄えた頃、主食として栽培されていたと考えられています。
その後、激動の歴史の中でキヌアの栽培は大幅に減少しましたが、アンデス地域の人々を中心にその栽培法は受け継がれています。
1990年代になって、NASA(アメリカ航空宇宙局)が宇宙空間での長期滞在に適した作物と発表したことで一躍脚光を浴びました。
そして、2013年には国連が飢餓対策の重要作物として「国際キヌア年」を設定し、最近では国際的に注目が高まっている作物なのです。

 キヌアは別名「奇跡の穀物」と呼ばれています
キヌアは別名「奇跡の穀物」と呼ばれています
冒頭で紹介したニュースはまさに、キヌアの高い環境適応性や優れた栄養特性を支えるメカニズムを活かし、不良環境耐性作物の開発や、栄養改善に向けた作物開発の研究が進むことが期待されている証

食糧の問題は世界的な課題のひとつですから、今後どんな研究が進んでいくのか気になるところですね

最近では大きなスーパーマーケットでも販売されるようになり、身近な存在になりつつあるキヌア。
見た目は「あわ」や「キビ」に似て小粒で、粘り気はなく、ぷちっとした食感があり、とても食べやすいです。
その栄養価の高さには目を見張るものがあります。
例えば、白米と比較してみると、タンパク質は約2倍、食物繊維は約10倍、鉄分は4倍以上、カルシウムは6倍。
これだけでも栄養価が高いことが分かりますが、さらに体内で作れない「9種類の必須アミノ酸」がすべて含まれているのです

またグルテンフリーなので、活用すればダイエット効果も期待できます

キヌアの調理方法ですが、私のオススメは「お米と一緒に炊く」ことです。
お米1カップに対し、ざっと水洗いして水切りしたキヌアを小さじ1〜大さじ1ぐらい加え、通常お米を炊くときと同じ量の水を加えて炊くだけなので、普段の食事に取り入れやすいですよ

さて今回は、お米と一緒にキヌアを炊くレシピ「きのこたっぷりのヘルシーピラフ」をご紹介します。

栄養価に優れ、ダイエット効果も期待できる「キヌア」を普段の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか

ぜひおためし下さいね



韓国の料理店では、メイン料理の前に出される小皿料理のことを、総称して「パンチャン」と言います。
このパンチャンの定番のひとつに「もやしナムル」があります。
もやしナムルは、韓国では大豆もやしを使うのが主流ですが、日本では緑豆もやしのナムルを目にする機会が多いのではないでしょうか。
日本ではもやしの姿がおなじみの緑豆ですが、韓国ではもやしを発芽
 させる前の「緑豆」も、料理によく使われているんですよ
させる前の「緑豆」も、料理によく使われているんですよ
 緑豆料理で代表的な物は「ピンデトック(緑豆チヂミ)」で、ソウル中心部の広蔵市場(クァンジャンシジャン)では名物料理になっています。
緑豆料理で代表的な物は「ピンデトック(緑豆チヂミ)」で、ソウル中心部の広蔵市場(クァンジャンシジャン)では名物料理になっています。緑豆チヂミは、一晩水に浸けた緑豆を電動の石臼で細かく挽いて生地にし、もやしなどの野菜や肉を入れて、たっぷりの油で揚げるように焼きます。
これを酢じょうゆで食べると、油っぽさがなくなっておいしく頂けます

緑豆チヂミ以外では、丸鶏のお腹に緑豆を詰めてサムゲタンにすることも。
サムゲタンは高麗人参、ニンニク、なつめ、もち米などが入った夏の滋養料理です。
もち米の代わりに緑豆を詰めることで、ぐっと栄養価が高くなります


 緑豆は漢方薬としても使用されていて、漢方では身体を冷やす作用があると言われています。
緑豆は漢方薬としても使用されていて、漢方では身体を冷やす作用があると言われています。また体内にたまった余分な水分も排出するため、むくみ防止も期待できます。
身体にこもった熱を冷まし、余分な水分を出してくれるので、これから暑くなる季節にピッタリの食材ですね

 さらに「健康」・「美容」にも良い効果があります。
さらに「健康」・「美容」にも良い効果があります。緑豆の鉄分はほうれん草の約3倍もあり、貧血で悩んでいる方や、鉄分が不足している方にオススメです。
また食物繊維を豊富に含むため、腸内をデトックスして整え、美肌効果も期待できます

他にも、アルコールを摂取したときに、アルコールの分解を促進してくれるので、二日酔いになりにくくなります。
二日酔いと言えば、韓国では二日酔いを冷ますスープのことを「解腸汁(ヘジャンクク)」と呼び、地方ごとに材料や調理方法が違いますが、牛の骨で出汁を取ったスープに味噌を加え、大豆もやし・大根・白菜・ネギなどを入れて煮た物が代表的で、緑豆を入れたスープも、解腸汁としてよく食されています。
お酒を飲みすぎてしまったときは、緑豆の解腸汁で二日酔いが防げるかもしれませんね

普段の食生活では緑豆もやし、緑豆春雨を料理に利用することが多いと思いますが、たまには気分を変えて、緑豆を活用してみてはいかがでしょうか

さて今回は、緑豆を使ったレシピ、「緑豆チヂミ」をご紹介します。

皮むきの緑豆を使えば調理しやすく、手軽に韓国本場のチヂミを味わえますよ

焼きたてのチヂミの味は格別です

ぜひお試し下さいね


こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。
4月に入って紫外線の量が増え、お肌への影響が気になる季節になってきましたね
日焼け止めを塗ったり、日傘を差したり、サプリメントを摂ったり、何らかの紫外線対策をしている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「ビタミンCと紫外線対策」についてご紹介します。
ビタミンCは皮膚と関係が深く、肌の美容には欠かせない栄養素。
皮膚にはコラーゲンがたくさん含まれており、コラーゲンの生成と維持にビタミンCが不可欠です。
また肌の色も、ビタミンCと関係があると言われています。
紫外線の多い直射日光に皮膚をさらすと、濃色のメラニンが増え、肌色が黒くなります。
シミは、この濃色のメラニン色素が皮膚に沈着した物です
メラニンは、チロシンというアミノ酸から生成されますが、ビタミンCがチロシンに働きかけると、メラニンの生成を抑えます。
そのためビタミンCを摂ると、シミのない美しい肌を保つことができると言われているのです
美しい肌を保つには、まず紫外線を防ぎ、そしてビタミンCを十分に摂ることが大切です
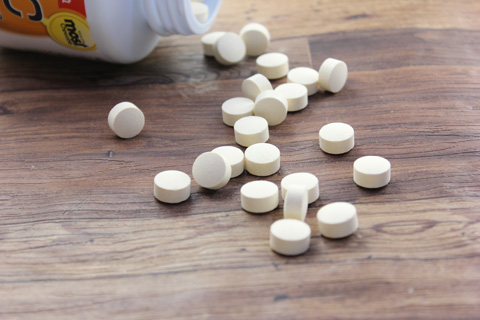
ビタミンCは体内で合成できない物質のため、食事やサプリメントから摂る必要があります。
毎日の食事からビタミンCを十分に摂れれば理想的ですが、不足しがちな場合はサプリメントを上手に活用しましょう
ただし、ビタミンCのサプリメントと一口に言っても、製品によって種類が違いますので、見極めが肝心です。
例えば、天然ビタミンCと合成ビタミンCです。
多くの栄養素は化学合成で同じ分子構造を持った物を作ることができ、ビタミンCも例外ではありません。
天然ビタミンCは合成ビタミンCに比べて抽出するのに手間がかかるため、市場に出回っているビタミンCサプリメントの多くが合成ビタミンCです。
天然も合成もビタミンC自体の働きに違いはありませんが、天然ビタミンCは原料(果実など)に含まれているビタミンC以外の成分を含み、それが相乗効果を生んで体になじみやすく、吸収率が良いと言われています。
天然ビタミンCは、原材料名に抽出した果実類の「ローズヒップ」や「アセロラ」等が記載されている場合が多いです。
合成ビタミンCは、原材料名に「ビタミンC」と成分名そのものが記載されている場合が多いようです。
サプリメントを選ぶときは、原材料名をチェックすると良いでしょう
 最後に、ビタミンCを活用して紫外線対策するポイントを2つお伝えします。
最後に、ビタミンCを活用して紫外線対策するポイントを2つお伝えします。 こまめに摂取する
こまめに摂取する
ビタミンCは非常にデリケートで、水、熱、光、酸素、喫煙の刺激にも弱く壊れやすい栄養素です。
また、ビタミンCは水溶性で代謝のサイクルが早く、一度にたくさん摂っても体内に溜めることができません
この性質を考慮し、最近ではタイムリリース型、持続型といった体内で少しずつ溶けるタイプのサプリメントも増えています。 旬の野菜や果物を摂る
旬の野菜や果物を摂る
旬の食材は、全体的に栄養価がぐっと高まります
野菜や果物からビタミンCをたくさん摂るには、旬の時期を逃す手はありませんよ
今の時期なら、春キャベツ、ブロッコリー、イチゴ、キウイフルーツなどがおすすめです
さて今回は、ビタミンCが豊富な食材を使った「グリーンピースのクリームパスタ」をご紹介します。
今が旬のグリーンピースは、緑色が目にも鮮やか
生クリームと白ワインで作るパスタソースは、簡単なのに本格的な味わいですよ。
ぜひお試しを


こんにちは!料理家の竹内ひろみです。
新年度を迎える4月は、「いろいろなことに挑戦しよう!」と気持ちも改まりますよね
しかしそんな気持ちとは裏腹に、なんとなく調子が出ない、元気が出ない… ということはありませんか?
ということはありませんか?
もしかするとそれは「未病」のサインかもしれません
未病とは東洋医学の考え方のひとつで、体がだるい、疲れやすい、冷え、頭痛、めまい、不眠などといった不調を抱えている状態のことです。
未病の原因のひとつに、胃腸の働きが悪くなることが挙げられます。
活動するエネルギーは、胃腸で食物を消化吸収して作られるため、胃腸が不調だと、やる気や元気を起こすエネルギーをうまく作れず、病院に行くまでもないけれど、なんとなく体調が優れない状態になるのです
そして、胃腸の働きは自律神経の状態にも影響を与えます。
春は特に環境が変わるなどでストレスが増え、自律神経が乱れやすくなる季節と言われています。
乱れた自律神経の影響を受けて胃腸の働きが弱くなり、エネルギー不足が自律神経のバランスを崩すという悪循環を起こすことも

胃腸は冷えに弱いため、胃腸を冷やさないことが大切な養生のひとつです
胃腸は冷えると正常に働かないばかりか、免疫力が低下し、風邪を引きやすくなったり、アレルギー症状を引き起こしたりします。
例えば東洋医学では、アレルギー症状を抑える薬に、胃腸を温める漢方薬が用いられています。
胃腸の健康が食べ物で作られることは、言うまでもありませんね
極端に辛い物などの刺激物や、精製されている物、生ものなど体を冷やす食べ物を控えるなど、胃腸に負担をかけない食生活がおすすめです
例えばレタスは、生で頂くことが多い野菜ですが、スープに入れたり、ご飯と一緒に炒めて炒飯にしたり、火を加えて温かい料理に変更してみて下さい。
毎日の食事には、加熱調理する料理を織り交ぜ、調理方法や食べ方が偏らないように心がけると良いでしょう
さて今回は、「炒めゴボウとひじきのご飯」をご紹介します。
ゴボウもひじきも食物繊維が豊富で、体を温める食材でもあり、胃腸を整えてくれますよ
ゴボウとひじきと聞いて和風を想像する方もいらっしゃると思いますが、ちょっと工夫して、味付けは洋風にしました!
ぜひお試し下さい




























