こんにちは。野菜と豆腐の料理家あらため、豆腐料理研究家の江戸野陽子です
こちらで豆腐料理を紹介するようになってから、豆腐をメインに扱うようになりまして、肩書きを「豆腐」オンリーにすることにしました。
とは言え、活動内容は今までと変わりません。
どうぞよろしくお願いします
さて、今回は豆腐の発祥地について話したいと思います。 豆腐の起源は中国にあり
豆腐の起源は中国にあり
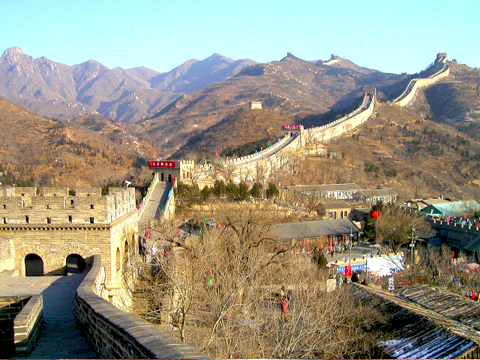
豆腐の起源にはいくつかの説があります。
そのなかで、有力と言われるものはふたつあります。 紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている
紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている
 豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。
豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。
このように豆腐は、少なくとも唐代中期頃に作られていたと言われているようです
 中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!
中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!

日本には木綿、絹ごし、おぼろ、充填豆腐など、色んな種類の豆腐がありますが、中国はそれ以上と言われています。 よく知られている豆腐は、以下のような物があります。
よく知られている豆腐は、以下のような物があります。 嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐
嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐 老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐
老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐 豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。
豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。 豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。
豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。 臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。
臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。 腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。
腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。
料理によく活用されているのが、老豆腐なのですが、これは日本の木綿豆腐より固くて水分が少なめなのが特徴です。
それもこれも、中国では豆腐を加熱調理(揚げる、焼く、煮る)することが多く、水分がない方が良いからなのだと思っております。
実際、本場中国の麻婆豆腐を食したことのある方々は、「麻婆豆腐の豆腐は、水分が抜けてスポンジに近い状態になっていて、そこに味が染み渡っていて、おいしいんだ」と、教えてくれます
 木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう
木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう

そこで今回は、水切りした木綿豆腐を使って作る「四川麻婆豆腐」をご紹介したいと思います
ポイントは、木綿豆腐をレンジで加熱してから水切りすること
鍋で沸かしたお湯でゆでるより、レンジの方がしっかりと水切りができるので、レンジをオススメしています。
木綿豆腐をキッチンペーパーで包んでから加熱し、重しを乗せて、しっかりと水切りしてあげて下さい。
こうすることで味が豆腐に絡みやすくなり、かつ崩れにくい四川麻婆豆腐が作れますので、ぜひお試し頂けたらと思います


こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです

メタボリックシンドローム、体脂肪、中性脂肪、BMIなど、身体の健康にかかわる言葉は皆さんご存じだと思います

体内脂肪に関係の深い用語ですね。
体内脂肪と聞くとあまり良いイメージはないかと思いますが、脂肪は栄養を蓄える貯蔵庫、体温保持、衝撃から身体を守るなど、身体にとってはなくてはならない物です。
しかし、増えすぎてしまうと、体形の問題以上に様々な病気の要因となってしまいます


 そもそも、何故、脂肪はついてしまうのでしょうか?
そもそも、何故、脂肪はついてしまうのでしょうか?
人は食事で得られる栄養をエネルギー源とし、身体を動かしていますが、筋肉や内臓が必要としている以上の栄養を摂ると、それらはいざというときに使うための体脂肪として蓄えられます
また、体脂肪を構成する脂肪細胞は、膨らんで大きくなると分裂をしますが、このサイクルが繰り返されることで、体脂肪はいくらでも増えてしまうのです
 体脂肪の主な原因は糖質や脂質の摂りすぎですが、今回は「脂質」についてお話していきたいと思います。
体脂肪の主な原因は糖質や脂質の摂りすぎですが、今回は「脂質」についてお話していきたいと思います。
脂質は、動物性脂肪と植物性脂肪のふたつに代別されます。
「どちらが健康に良いのか?」と言う二極論になりがちですが、ポイントは油を構成する脂肪酸。
動物性脂肪は、バター、ラード、肉の脂身に代表され、「飽和脂肪酸」と呼ばれています。
一方で植物性脂肪は、オリーブ油、サラダ油、魚油などがあり、「不飽和脂肪酸」と呼ばれています。
どちらも最終的には体脂肪となるため、バランス良く摂取することが基本です
 さて、そのなかで「必須脂肪酸」と言って、私たちの身体では合成することができない油をご存知でしょうか
さて、そのなかで「必須脂肪酸」と言って、私たちの身体では合成することができない油をご存知でしょうか
必須脂肪酸には、オメガ6系脂肪酸(リノール酸 ごま油、紅花油など)と、オメガ3系脂肪酸(α-リノレン酸、えごま油、亜麻仁油、EPA、DHA)の2種類がありますが、近年オメガ6脂肪酸の摂りすぎが問題となっており、オメガ6脂肪酸を減らし、オメガ3脂肪酸を摂ることが推奨されているのです
オメガ3系脂肪酸は酸化されやすいので、生食が適していますよ
オメガ9系脂肪酸(オレイン酸)にはオリーブオイルがあります。
こちらは体内でも合成が可能な脂質ですが、悪玉コレステロールの濃度を減らす働きがあるので、しばしば身体に良い油と取り上げられていますね。
店頭には、様々な種類のオリーブオイルが並んでいて値段もまちまちですが、大きく分けると、エキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルがあります。
エキストラバージンオリーブオイルは、オリーブの実の生絞りですので、そのまま生使いが風味を味わう上ではおいしい食べ方です
一方のピュアオリーブオイルは、精製過程でポリフェノールなどが取り除かれているので、風味は劣りますが、酸化しづらくなっているので、炒め物、揚げ物など、火を使う料理に使えます
脂質の特性を知って、上手に使い分けると、おいしさはもとより、健康効果がさらににアップしますよ
さて、本日のレシピは、ヘルシーでお腹満足の食べるサラダ、「ナッツのホットサラダ」をご紹介致します
皆さんも、ぜひお試し下さい


こんにちは
野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。
今年も豆腐の魅力について、たくさんお話しできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします
早速ですが、豆腐の魅力と言えば「大豆」の話は外せません。
豆腐の原材料である大豆は、味を左右する決め手と言っても過言ではないでしょう。
昨年、岡山で第5回全国豆腐品評会が開催されましたが、そこで集結した全国トップクラスの味を誇る豆腐たちのどれもが、こだわりの大豆で作られていました。
使っている物は、地元で作られている地域限定の大豆だったり、全国的に知られている銘柄大豆だったりと、本当に様々です。
ズラリと並ぶ豆腐を味見して、これからは大豆のことを伝えたいと思いました。 パッケージから大豆の表記を確認してみよう!
パッケージから大豆の表記を確認してみよう!

大豆の品種で豆腐を選んでいる人は、それほどいないのではないかと思いますが、じつは条件は揃っています。
手元に豆腐があれば、パッケージにどんな大豆が記載されているのか見てみて下さい
「国産大豆」、「カナダ産大豆」、「アメリカ産大豆」などの、大豆の産地を記載している物もあれば、「とよまさり」、「フクユタカ」、「サチユタカ」など、大豆の品種を記載している物もあります。
そして、さらに詳細な物となると、「北海道産とよまさり」、「九州産フクユタカ」と言った具合に、地域と産地が記載されている物もあるでしょう。
このように、パッケージから大豆の情報が発信されています
しかし、大豆の種類が分かったところで、味は相当ツウな方でない限り分かりにくいのではないでしょうか。
それでも、イチゴは品種名を言えば味が想像できるし、お米はブランド名と産地を聞けば、その価値が分かる方がいるように、種類で味が判断できる物もあるので、豆腐における大豆も、そういった風潮になったら良いなと思っております。
では、実際に豆腐と大豆と味の関係についても解説していきましょう。 どの大豆の豆腐がおいしいの?
どの大豆の豆腐がおいしいの?

どんな大豆でも豆腐は作れますが、「甘み」と「タンパク質」の両方が多い大豆から、おいしい豆腐が作れると言われております。
「甘み」とは、糖分の量のことで、豆腐の甘さに直結します。
昨年の豆腐品評会では、宮城県産「ミヤギシロメ」を使っている豆腐が多く見られました。
じつは宮城県は、大豆の栽培面積が2位
なかでも「ミヤギシロメ」は、味と風味が良く、県では奨励品種(普及してほしい品種)に指定されている大豆です。
この大豆は、ショ糖含有量が8.1(乾物中の%)で、他の大豆が5.0〜8.0であることから比べると、なかなか高い数値を誇っています
さて、数値の話よりも実食した話をしますね。
100品以上の豆腐が出品されているなか、7品ほどが「ミヤギシロメ」を使っており、そのどれもが強い甘みとコクがあり、ひと口でそのおいしさが分かるほどの味です。
そして私に「ミヤギシロメ」はおいしい、という印象を強く残しました
 私のおすすめの大豆
私のおすすめの大豆
ちなみに、個人的なオススメの大豆は、枝豆の風味を思わせる緑豆の「キヨミドリ」。
ゆでたての枝豆のようなあと味で、強い味わいがお気に入りです
次に、兵庫と岡山で作られている「もち大豆」。
これは、限られた地域でしか作られていない大豆なのですが、甘みとコクをかね備えており、満足するおいしさを持つ豆腐だと思っております。
今お話しした2つの大豆は、豆腐屋さんで扱っていることが多いので、スーパーなどで購入するのなら、「北海道産とよまさり」の豆腐や、「九州産フクユタカ」の豆腐がオススメです。
いずれも、高い糖分を持つことで知られており、たくさん作られているので、手頃なお値段で手に入ります。
大豆の甘みをしっかりと感じることができるので、オススメですよ
今回は、豆腐の風味を存分に味わえる「豆腐のあんかけ」をご紹介致します
絹ごしでも木綿でも、お好みの豆腐を用意しましょう。
写真は、私オススメのキヨミドリの豆腐で作っています。
豆腐はパッケージから取り出したら、一度キッチンペーパーの上に取り出して水分を吸わせましょう!
こうすることで、豆腐から出てくる水分で味が薄まることを防止できます。
食べる直前に、電子レンジで温めていますが、蒸し器があればそれでもOKです。
仕上げに出汁をきかせたあんかけと、たっぷりの薬味を乗せて頂きます!温かい豆腐にあんが絡まって、豆腐のおいしさを実感できますよ


こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。
さて、2020年に入り最初のブログ記事になりますが、今年は7月24日〜8月9日までの間、「東京五輪2020」が開催されます

今から夏が楽しみですね!
さて、私は管理栄養士、フードコーディネーターとして、「食」や「健康」をテーマにお仕事をしていますので、年末から年始にかけて前年の食のトレンドを振り返ったり、新年の新しい食のトレンドを調べることが毎年の習慣になっています

そこで2020年1回目となる今回のブログは、「2019年のフードトレンドを振り返りつつ、2020年のフードトレンド予想について」をご紹介します。

 それではまず、2019年の食のトレンドをいくつかの発表をもとに振り返っていきましょう。
それではまず、2019年の食のトレンドをいくつかの発表をもとに振り返っていきましょう。2019年12月にある会社から発表された「食トレンド大賞2019」によりますと、2019年は節約、時短、簡単である「献立のシンプル化」が進み、一汁一菜でおいしく健康に過ごせる献立や、具沢山で栄養バランスが取れたり、満足感が得られる「ごちそうおにぎり」などが人気を集めたようです。
また、高級食パンを家で再現するレシピや、保存袋で作る簡単な梅干しのレシピなども人気となりました。
この結果から、家事や育児、仕事で忙しい日々でも、おいしい食パンや簡単に手作りできる保存食などで、「ささやかなこだわりや丁寧な暮らしを楽しみたい」と言う気持ちが表れていることがよく分かります。
また、株式会社ぐるなび総研から発表された2019年の「今年の一皿(登録商標)」では、やはり一世を風靡した「タピオカ」が選ばれました。
タピオカが選ばれた理由として、「タピる」、「タピ活」などの造語が生まれ、ブームを超えて社会現象化したことや、様々な飲み物との相性が良く、好みに応じてカスタマイズできることから消費者の楽しみが広がったことなどが挙げられています。
タピオカやツェーなど、アジアンフードは引き続き2020年も人気になるようです。
 それでは、いよいよ2020年のトレンドについてご紹介していきます。
それでは、いよいよ2020年のトレンドについてご紹介していきます。2019年10月下旬、アメリカを中心にカナダとイギリスを含め、270店鋪以上を展開する「ホールフーズ・マーケット」 が2020年の食品トレンド予測を発表しました。
それによりますと、2020年は「再生農業」やエチオピア料理に使用されるテフパウダー、カリフラワーパウダー、バナナパウダーなどの「新しい小麦粉代替品」、アメリカでは、トマト、タマネギ、唐辛子、ピーナッツ、レモングラスなどを使った「伝統的な西アフリカ料理」が人気になっています。
それに伴い、モリンガ、タマリンド、ソルガム、フォニオ、テフ、キビなどの「西アフリカの食品」、緑豆、ヘンプシード、カボチャ、アボカド、スイカの種、ゴールデンクロレラなどの「大豆に変わる植物性食品」がランクインするなどとても興味深い内容となっています。
アメリカの食のトレンド予想ですが、実際にどの程度日本で流行するのでしょうか

今からとても楽しみですね

さて、話を日本に戻しまして、先ほどご紹介したクックパッド株式会社から発表された「食トレンド予測」によりますと、2020年は引き続き台湾や韓国といったアジアをはじめとする料理が人気を集める年になると予測されています。
他にも、シェントウジャン、食品ロス削減、レーリュッケン、チーズボール、スイカジュースなどが2020年のトレンドキーワードとして選出されています。
今年は五輪イヤーということもあり、訪日観光客の目標は4,000万人と言われています。訪日外国人が自国の食文化を日本に持ち込むなど、食の多様化、グローバル化が進むことが予想されます。
これらのトレンドも参考にしながら、2020年も様々な食や健康の情報をもとに、皆様にお役立て頂けるブログをお届けしていきたいと思っています

 最後に、すでに2019年から流行し、テレビなどで取り上げられて話題になっている「発酵鍋」はご存知でしょうか?
最後に、すでに2019年から流行し、テレビなどで取り上げられて話題になっている「発酵鍋」はご存知でしょうか?ここ数年、健康志向の高まりにより発酵食品が注目されています

「発酵鍋」は、味噌や麹といった日本の伝統食品や、キムチ、ヨーグルト、チーズなどの様々な発酵食品を、具材や付けダレに使用した鍋のことを言います。
「発酵鍋」は、発酵食品の持つ、まろやかで深い味わいや旨みを利用し、おいしい鍋スープが手軽にできることや、発酵食品どうしの組み合わせにより、味のバリエーションが豊富で飽きることがなく楽しめることなどが人気の理由です。
また、発酵食品に含まれる乳酸菌などの善玉菌には、腸内の環境を整える作用が期待できるため、便秘の解消や免疫力アップに効果が期待できますよ

具材に火が通ってから最後に発酵食品である納豆を加えた「納豆鍋」や塩麹をベースにした「塩麹鍋」、ヨーグルトを付けダレに加えた物など、様々な「発酵鍋」のバリエーションが考えられます。
お好みの発酵食品を使って、寒い冬を温かいお鍋で元気に乗り切りましょう

今回ご紹介している「キムチーズ味噌鍋」は、発酵食品であるキムチ、チーズ、味噌を使用しています。
チーズがキムチの辛さをまろやかにしてくれるのでお子様にも人気のお鍋です。
トマトベースのお鍋なので、シメはご飯を入れてリゾットにするのがオススメですよ。
皆さんも、ぜひお試し下さい





























