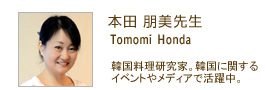2019/03/14
こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
東アジアの食文化は、「中国大陸」→「朝鮮半島」→「日本」の経路で広まった物が多いですが、各国の環境的な要素が加わって根付いたり、変化したりしました
緑茶も同様のルートで伝わりましたが、韓国よりも日本で発展した文化のひとつです。
緑茶と仏教は深い結び付きがあったため、仏教から儒教に移行した朝鮮時代(1392〜1910年)に緑茶文化が衰退し、薬茶文化が始まりました
薬茶とは、茶葉を使わずに韓方薬を煎じた物で、伝統茶とも言います。朝鮮時代の初期は王様や貴族中心に飲まれていましたが、18世紀以降は庶民に薬草の知識が普及し、広く愛飲されるようになりました。
とは言え、庶民は経済的な負担を軽くするために、一種類のみを使う単方が主流で、王様や貴族は数種類を組み合わせて飲用しました。
以前ご紹介したブログで、王様が好んで使った韓方材は「高麗人参(=朝鮮人参)、橘皮(きっぴ)、ショウガ、桂皮(けいひ)」と書きましたが、一番使われたのはどれだと思いますか?
それは「高麗人参」です

王室では苦い薬ばかり服用していると、かえって食欲を失ってしまい治療にならないと考えられていました。そのため、元気を補うための食治として重要視したのです。
高麗人参の効能は
 性質は「温」で体を温める。
性質は「温」で体を温める。
 体力不足で虚弱になった場合、元気を補う。
体力不足で虚弱になった場合、元気を補う。
 胃の調子の悪化による食欲不振、下痢、嘔吐を治める。
胃の調子の悪化による食欲不振、下痢、嘔吐を治める。
 体の水分や血液の不足で衰弱している場合、体内の水分バランスを整える。
体の水分や血液の不足で衰弱している場合、体内の水分バランスを整える。
 イライラや不眠を解消し、精神安定を図る。
イライラや不眠を解消し、精神安定を図る。
高麗人参については単方のお茶が一番飲まれていましたが、二種類以上組み合わせた物もありました。
 黄耆人参茶(黄耆+朝鮮人参)
黄耆人参茶(黄耆+朝鮮人参)
黄耆(おうぎ)は参鶏湯を煮込むときに良く使う韓方材で、高麗人参と同じように胃を整えて体力を回復させます。黄耆も体を温める働きがあるので、風邪による食欲不振のときに摂取するのがお勧めです。
 参橘茶(さんきゅるちゃ)(朝鮮人参+橘皮)
参橘茶(さんきゅるちゃ)(朝鮮人参+橘皮)
みかんの皮を干した橘皮(きっぴ)は、気血の巡りを良くして体を温め、食欲を促進します。香りには精神を安定させる働きがあります。
 四味茶(朝鮮人参+ショウガ+橘皮+ナツメ)
四味茶(朝鮮人参+ショウガ+橘皮+ナツメ)
韓国料理に良く使われるナツメは、造血作用によりストレスを解消します。また胃腸の機能を良くして元気を付けます。
今回ご紹介したのはほんの一部で、朝鮮時代はすでに145種類の薬茶がありました。
日本では薬でも、韓国では食品として扱われている韓方材が多くあるので、身近な存在です
私自身、韓国から仕入れた薬茶を毎日飲んでいるので、元気なのかもしれません。
それでは、本日のレシピをご紹介致します!
「高麗人参とショウガのハチミツ茶」です。薄切りにした高麗人参とショウガをハチミツ漬けにした物で、作るのは簡単ですが、完成までにちょっと時間がかかります。
しかし、完成した味わいは格別です。高麗人参とショウガが生でも食べられるのもポイント

東アジアの食文化は、「中国大陸」→「朝鮮半島」→「日本」の経路で広まった物が多いですが、各国の環境的な要素が加わって根付いたり、変化したりしました
緑茶も同様のルートで伝わりましたが、韓国よりも日本で発展した文化のひとつです。
緑茶と仏教は深い結び付きがあったため、仏教から儒教に移行した朝鮮時代(1392〜1910年)に緑茶文化が衰退し、薬茶文化が始まりました
薬茶とは、茶葉を使わずに韓方薬を煎じた物で、伝統茶とも言います。朝鮮時代の初期は王様や貴族中心に飲まれていましたが、18世紀以降は庶民に薬草の知識が普及し、広く愛飲されるようになりました。
とは言え、庶民は経済的な負担を軽くするために、一種類のみを使う単方が主流で、王様や貴族は数種類を組み合わせて飲用しました。
以前ご紹介したブログで、王様が好んで使った韓方材は「高麗人参(=朝鮮人参)、橘皮(きっぴ)、ショウガ、桂皮(けいひ)」と書きましたが、一番使われたのはどれだと思いますか?
それは「高麗人参」です
王室では苦い薬ばかり服用していると、かえって食欲を失ってしまい治療にならないと考えられていました。そのため、元気を補うための食治として重要視したのです。
高麗人参の効能は
高麗人参については単方のお茶が一番飲まれていましたが、二種類以上組み合わせた物もありました。
黄耆(おうぎ)は参鶏湯を煮込むときに良く使う韓方材で、高麗人参と同じように胃を整えて体力を回復させます。黄耆も体を温める働きがあるので、風邪による食欲不振のときに摂取するのがお勧めです。
みかんの皮を干した橘皮(きっぴ)は、気血の巡りを良くして体を温め、食欲を促進します。香りには精神を安定させる働きがあります。
韓国料理に良く使われるナツメは、造血作用によりストレスを解消します。また胃腸の機能を良くして元気を付けます。
今回ご紹介したのはほんの一部で、朝鮮時代はすでに145種類の薬茶がありました。
日本では薬でも、韓国では食品として扱われている韓方材が多くあるので、身近な存在です
私自身、韓国から仕入れた薬茶を毎日飲んでいるので、元気なのかもしれません。
それでは、本日のレシピをご紹介致します!
「高麗人参とショウガのハチミツ茶」です。薄切りにした高麗人参とショウガをハチミツ漬けにした物で、作るのは簡単ですが、完成までにちょっと時間がかかります。
しかし、完成した味わいは格別です。高麗人参とショウガが生でも食べられるのもポイント