こんにちは!
管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。
4月に入って紫外線の量が増え、お肌への影響が気になる季節になってきましたね
日焼け止めを塗ったり、日傘を差したり、サプリメントを摂ったり、何らかの紫外線対策をしている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「ビタミンCと紫外線対策」についてご紹介します。
ビタミンCは皮膚と関係が深く、肌の美容には欠かせない栄養素。
皮膚にはコラーゲンがたくさん含まれており、コラーゲンの生成と維持にビタミンCが不可欠です。
また肌の色も、ビタミンCと関係があると言われています。
紫外線の多い直射日光に皮膚をさらすと、濃色のメラニンが増え、肌色が黒くなります。
シミは、この濃色のメラニン色素が皮膚に沈着した物です
メラニンは、チロシンというアミノ酸から生成されますが、ビタミンCがチロシンに働きかけると、メラニンの生成を抑えます。
そのためビタミンCを摂ると、シミのない美しい肌を保つことができると言われているのです
美しい肌を保つには、まず紫外線を防ぎ、そしてビタミンCを十分に摂ることが大切です
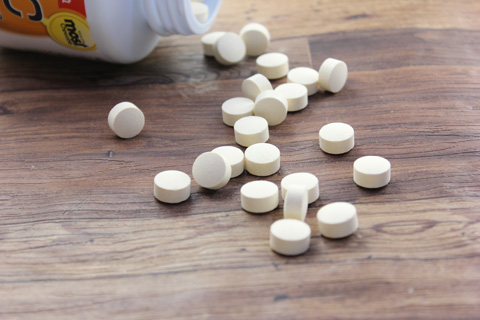
ビタミンCは体内で合成できない物質のため、食事やサプリメントから摂る必要があります。
毎日の食事からビタミンCを十分に摂れれば理想的ですが、不足しがちな場合はサプリメントを上手に活用しましょう
ただし、ビタミンCのサプリメントと一口に言っても、製品によって種類が違いますので、見極めが肝心です。
例えば、天然ビタミンCと合成ビタミンCです。
多くの栄養素は化学合成で同じ分子構造を持った物を作ることができ、ビタミンCも例外ではありません。
天然ビタミンCは合成ビタミンCに比べて抽出するのに手間がかかるため、市場に出回っているビタミンCサプリメントの多くが合成ビタミンCです。
天然も合成もビタミンC自体の働きに違いはありませんが、天然ビタミンCは原料(果実など)に含まれているビタミンC以外の成分を含み、それが相乗効果を生んで体になじみやすく、吸収率が良いと言われています。
天然ビタミンCは、原材料名に抽出した果実類の「ローズヒップ」や「アセロラ」等が記載されている場合が多いです。
合成ビタミンCは、原材料名に「ビタミンC」と成分名そのものが記載されている場合が多いようです。
サプリメントを選ぶときは、原材料名をチェックすると良いでしょう
 最後に、ビタミンCを活用して紫外線対策するポイントを2つお伝えします。
最後に、ビタミンCを活用して紫外線対策するポイントを2つお伝えします。 こまめに摂取する
こまめに摂取する
ビタミンCは非常にデリケートで、水、熱、光、酸素、喫煙の刺激にも弱く壊れやすい栄養素です。
また、ビタミンCは水溶性で代謝のサイクルが早く、一度にたくさん摂っても体内に溜めることができません
この性質を考慮し、最近ではタイムリリース型、持続型といった体内で少しずつ溶けるタイプのサプリメントも増えています。 旬の野菜や果物を摂る
旬の野菜や果物を摂る
旬の食材は、全体的に栄養価がぐっと高まります
野菜や果物からビタミンCをたくさん摂るには、旬の時期を逃す手はありませんよ
今の時期なら、春キャベツ、ブロッコリー、イチゴ、キウイフルーツなどがおすすめです
さて今回は、ビタミンCが豊富な食材を使った「グリーンピースのクリームパスタ」をご紹介します。
今が旬のグリーンピースは、緑色が目にも鮮やか
生クリームと白ワインで作るパスタソースは、簡単なのに本格的な味わいですよ。
ぜひお試しを


こんにちは!料理家の竹内ひろみです。
新年度を迎える4月は、「いろいろなことに挑戦しよう!」と気持ちも改まりますよね
しかしそんな気持ちとは裏腹に、なんとなく調子が出ない、元気が出ない… ということはありませんか?
ということはありませんか?
もしかするとそれは「未病」のサインかもしれません
未病とは東洋医学の考え方のひとつで、体がだるい、疲れやすい、冷え、頭痛、めまい、不眠などといった不調を抱えている状態のことです。
未病の原因のひとつに、胃腸の働きが悪くなることが挙げられます。
活動するエネルギーは、胃腸で食物を消化吸収して作られるため、胃腸が不調だと、やる気や元気を起こすエネルギーをうまく作れず、病院に行くまでもないけれど、なんとなく体調が優れない状態になるのです
そして、胃腸の働きは自律神経の状態にも影響を与えます。
春は特に環境が変わるなどでストレスが増え、自律神経が乱れやすくなる季節と言われています。
乱れた自律神経の影響を受けて胃腸の働きが弱くなり、エネルギー不足が自律神経のバランスを崩すという悪循環を起こすことも

胃腸は冷えに弱いため、胃腸を冷やさないことが大切な養生のひとつです
胃腸は冷えると正常に働かないばかりか、免疫力が低下し、風邪を引きやすくなったり、アレルギー症状を引き起こしたりします。
例えば東洋医学では、アレルギー症状を抑える薬に、胃腸を温める漢方薬が用いられています。
胃腸の健康が食べ物で作られることは、言うまでもありませんね
極端に辛い物などの刺激物や、精製されている物、生ものなど体を冷やす食べ物を控えるなど、胃腸に負担をかけない食生活がおすすめです
例えばレタスは、生で頂くことが多い野菜ですが、スープに入れたり、ご飯と一緒に炒めて炒飯にしたり、火を加えて温かい料理に変更してみて下さい。
毎日の食事には、加熱調理する料理を織り交ぜ、調理方法や食べ方が偏らないように心がけると良いでしょう
さて今回は、「炒めゴボウとひじきのご飯」をご紹介します。
ゴボウもひじきも食物繊維が豊富で、体を温める食材でもあり、胃腸を整えてくれますよ
ゴボウとひじきと聞いて和風を想像する方もいらっしゃると思いますが、ちょっと工夫して、味付けは洋風にしました!
ぜひお試し下さい

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です

4月に入り新年度がスタートしました。
就職・進学などで新しい環境での生活が始まった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
新しい環境に慣れるまでは何かと忙しく、食事さえ疎かになってしまうこともあると思いますが、忙しい時期だからこそ、しっかり食べて健康には気を付けたいものですね

健康に良い定番食品と言えば「大豆製品」。
大豆は身体の血液や肉体を作るのに欠かせない、良質なタンパク質を豊富に含んでおり、またタンパク質は生きていくために欠かせない、重要な栄養素なのです

そこで今回は、大豆製品の中でも特に日本人になじみ深い「豆腐」についてご紹介します。
豆腐は、食品売り場に様々な種類が並んでいますね。
○○豆腐と名の付く食品がたくさんある中、よく見かけるのが「絹ごし豆腐」と「木綿豆腐」ですが、これらの豆腐の名前の由来をご存知でしょうか

文字通り、絹ごし豆腐は絹の布、木綿豆腐は木綿の布で豆乳をこした物、こんなイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、実際には食べたときの舌ざわりの違いから、「絹」と「木綿」と呼ばれるようになったそうです。
その違いを生み出すのは、豆腐の製造工程にあります。
 絹ごし豆腐は、木綿豆腐よりも濃い豆乳に凝固剤を加えて、そのまま固めて作ります。
絹ごし豆腐は、木綿豆腐よりも濃い豆乳に凝固剤を加えて、そのまま固めて作ります。そのため、きめ細かく滑らかな舌ざわりで、水分も多く含んでいるのが特徴です。
 木綿豆腐は、豆乳に凝固剤を加えて一度固めた物を崩してから、圧力をかけて水分を絞り、再び固めた物です。
木綿豆腐は、豆乳に凝固剤を加えて一度固めた物を崩してから、圧力をかけて水分を絞り、再び固めた物です。そのため、水分が少なくしっかりとした食感の楽しめる豆腐となっています。
圧縮されているため、栄養分も凝縮され、濃厚な味わいが感じられます。
この他にも、絹ごし豆腐と木綿豆腐の中間のやわらかさと滑らかさを持った「ソフト豆腐」や、木綿豆腐の工程の途中、崩す前の物を器に盛って製品とした「おぼろ豆腐」。
紐で結べる程堅く作られた「堅豆腐」、味がしみ込みやすく煮崩れしにくい「焼き豆腐」。
木綿豆腐を凍らせ、乾燥させて作る「高野豆腐」などがあります。
「堅豆腐」や「焼き豆腐」は煮物や炒め物に、「高野豆腐」は煮物、揚げ物や汁物に向いていますよ

 豆腐を製造する過程で、一般的に2種類の添加物が使われています。
豆腐を製造する過程で、一般的に2種類の添加物が使われています。そのひとつは凝固剤で、豆腐を凝固させるために、豆腐製造には欠かせない物です。
昔は、酸類や海水から食塩を取った残りのニガリ(塩化マグネシウム)などの塩類を使うのが一般的でしたが、現在では、硫酸カルシウム、塩化カルシウムなども使われています。
これらは、豆腐の種類に応じて使い分けされているようです。
もうひとつの添加物は消泡剤で、砕いた大豆を加熱するとき生じる泡を消すために使用されています。
泡があると、食感の良いきれいな豆腐に仕上がらず、日持ちも悪くなるため、消泡剤が使われるようになりました。
また油脂系消泡剤、グリセリン脂肪酸エステル、シリコーン樹脂などがあり、目的に合わせて使用されています。
これらの消泡剤は、食品衛生法の基準に照らし合わせると、加工中に食品から除去されるか、最終食品に残っていても微量の場合、「加工助剤」として扱われ、原材料表示には記載されていないことがあります。
どの消泡剤も人体に有害ではありませんが、消泡剤を使っていない物を選びたい場合は、「消泡剤不使用」とパッケージに記載されている物を選ぶと良いでしょう

さて今回は、豆腐とイチゴを使ったデザート「豆腐フロマージュイチゴ添え」をご紹介。
 クリームチーズに豆腐を合わせることで、脂肪分を減らしてヘルシーに仕上げました
クリームチーズに豆腐を合わせることで、脂肪分を減らしてヘルシーに仕上げました
ぜひお試し下さいね


こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです
グリーンアスパラガスやエンドウ豆など、店頭に春野菜がずらりと並び、お買い物に行っても春 を感じる季節となりました。
を感じる季節となりました。
進学や就職、転勤、転職など、新生活がはじまるとともに、お弁当作りをはじめる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
家族や自分のために作るお弁当は、できればおいしい物を作りたいですよね
お弁当作りの悩みは人それぞれにあると思いますが、料理家の私がよく受ける質問があります
Q.お弁当に入れるおかずの品数を増やすにはどうしたら良い?
Q.お弁当箱の隙間をどうやって埋めたら良い?
といったもの。
そんなお悩みに対する答えは、「ひとつの野菜だけを材料に、おかずに変身させるレシピを覚えておく」ということです。
例えば、タマネギ、ピーマン、ニンジンで野菜炒めを作るとしましょう。
そのまま炒めれば1品ですが、これらの野菜をそれぞれに調理すれば3品になります。 タマネギは千切りにしてゴマ油で炒め、しょうゆ味にしてかつお節をふりかける。
タマネギは千切りにしてゴマ油で炒め、しょうゆ味にしてかつお節をふりかける。 ピーマンは拍子切りにしてニンニクとオリーブオイルで炒め、ハーブソルトをふりかける。
ピーマンは拍子切りにしてニンニクとオリーブオイルで炒め、ハーブソルトをふりかける。 ニンジンは棒状に切って、水と塩(甘くしたいときは砂糖)少々を加えて蒸し煮にし、砕いたナッツをからめる。
ニンジンは棒状に切って、水と塩(甘くしたいときは砂糖)少々を加えて蒸し煮にし、砕いたナッツをからめる。
調理法や味付けを変えることで、簡単に品数を増やせます
お弁当は、メインのおかずを肉や魚にすることが多いため、どうしても野菜が不足しがちです。
野菜だけで作れるおかずを知っておけば、おかずのバランスを考えるときや、お弁当箱の隙間にもう一品入れたいときにも重宝します

この方法は、お弁当のおかずだけでなく、普段の食卓に並べる料理にも応用できますよ
○○野菜だけで料理を作るコツを、もう少し詳しくお伝えします
コツ 調理方法を変えてみる
調理方法を変えてみる
調理方法には、焼く、炒める、揚げる、蒸す(電子レンジ調理)などがありますね。
ニンジンを例に挙げると、 千切りにして炒める
千切りにして炒める 輪切りにして蒸す
輪切りにして蒸す スティック状にして揚げる
スティック状にして揚げる
このように野菜の切り方や加熱法を変えるだけで、見た目や食感、味わいに違いが出て、別の料理になります
コツ 味付けを工夫する
味付けを工夫する
オーソドックスな塩・こしょう以外に、カレー粉を加えてみたり、ピリッと辛いコチュジャンを加えたり、ハーブソルトを使ってみたりと味にアクセントを付けると、同じ切り方や加熱法でもバリエーションの幅を広げることができます
コツ 風味や彩りを加える
風味や彩りを加える
ゴマやナッツ類(フードプロセッサーにかけて細かくした物)や、のり、ドライパセリ、くこの実などの食材を加えてみるのも良いでしょう。
ドライパセリは緑色、くこの実は赤色なので、盛り付けた料理に彩りを添える役割もかねてくれます!
野菜だけで作れる料理は、肉や魚など主菜の添え野菜にも使えるので、お好みに応じて色々作ってみて下さいね
さて今回は、○○野菜だけ料理「焼きネギのマリネ」をご紹介します。
焼いたネギの旨みが酸味のあるマリネとよく合います
細かくしたミックスナッツをふりかけて、風味にアクセントを付けました。
いつもとちょっと違うネギのおいしさをお楽しみ下さい



























