こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。
 李氏朝鮮時代、朝鮮半島は八道(パルド)と言って、八つの行政区に分かれていました。
李氏朝鮮時代、朝鮮半島は八道(パルド)と言って、八つの行政区に分かれていました。
現在の韓国と北朝鮮は、八道(パルド)を基礎として区分けされています。
朝鮮八道のひとつ、全羅道(チョルラド)は現在、全羅北道(チョルラプクド)と全羅南道(チョルラナムド)となりましたが、双方ともに農水産物が豊富であり、韓国料理の贅沢な食が味わえます
本日ご紹介したいのは、港町である全羅南道の木浦(モッポ)が産地として有名な、 「ガンギエイ」を使った料理です。
ガンギエイは韓国語で「ホンオ」と言いまして、韓国料理通の日本人の間では、お刺身のホンオフェと聞いただけで顔をしかめる人も
その理由は?
ホンオフェを作るためには、ガンギエイをワラに包んでカメに入れ、7〜10日程そのままおいて発酵させます。
できあがった時点で、独特なアンモニア臭を放っているんですね。
このにおいに苦手意識を持つ方がいらっしゃいます。
とは言え、韓国では 高級食材のひとつ
高級食材のひとつ であるため、全羅道のお祝い料理には欠かせないとか
であるため、全羅道のお祝い料理には欠かせないとか
もし、お祝いの席に用意されていなかったら「主催側が出し惜しみした」と陰口を叩かれるという話もあります。
ホンオフェの食べ方ですが、お酢入りのコチュジャンで生野菜と和えたり、三合(サマプ)と言って、ホンオフェとゆで豚を、熟成キムチで巻いたりします。
三合(サマプ)は何度か頂いたことがありますが、熟成キムチとゆで豚を組み合わせると、エイのにおいが和らいで食べやすくなります
韓国の地方は、珍しい料理がたくさんあります。
ソウル旅行を何度か楽しまれた方は、ぜひ地方にも足を伸ばして下さいね
それでは、今日のお料理をご紹介致します。
さすがにエイは用意できませんので・・・。
イカと生野菜を使った和え物「オジンオムチム」です。
レシピにあるお酢とコチュジャンを合わせたタレは、白身のお刺身にも合うので、レパートリーのひとつに加えて下さい

こんにちは!
料理家のひろろ こと 竹内ひろみです。
先日、子供のかかりつけのお医者さまを受診しました。
食品が病の原因のひとつと捉えているお医者さまなので、そのときも、「次回までにどんな物を食べているか食日記を付けてきて下さい」と言われました
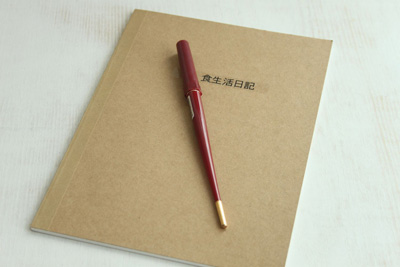
 早速、1日を振り返る時間に その日の食事内容を書き出してみました。
早速、1日を振り返る時間に その日の食事内容を書き出してみました。
毎日、記録しているとなんとなく習慣になり、4、5日分を振り返るといろいろな発見があり、興味深いです
食日記を付けてて良かった というメリットは主に3つ
というメリットは主に3つ
 ひとつは、「なんとなくダルイ、イライラする・・・」というとき、ちょっとした不調の原因が分かったりするのです
ひとつは、「なんとなくダルイ、イライラする・・・」というとき、ちょっとした不調の原因が分かったりするのです
例えば、体調がスッキリしない場合、動物性食品に偏っていたり、添加物が多い物を摂取していたりすることが多いんです。
 二つめは、ダイエットには最適な方法です。
二つめは、ダイエットには最適な方法です。
「今日の食事も記録しなければ!」と意識して食事をすれば、食べたい気持ちにブレーキがかかると思うのです
空腹による食欲もありますが、あまり空腹じゃなくても「おいしそう〜」と誘惑されてつい余分に食べてしまうときがありますよね
そんなとき、日記を振り返ってみると、「やっぱり○○が多かったな。ちょっと○○をコントロールしよう!!」という感じで食生活を正す目安にもなるのです。
 最後は、 お財布管理にも効果的
最後は、 お財布管理にも効果的
それは、余計な物を購入=余計な物を食べている ・・ということが分かるからです。
日記を見直すとことにより、買い物のときに、必要な物だけカゴに入れてレジに直行(私だけかな??)できるのです
毎日記録するのはけっこう大変かな とも思いますが、1、2週間位続けてみられることをおすすめします
とも思いますが、1、2週間位続けてみられることをおすすめします
さて、本日のレシピは私の食日記の中から、暑い夏をおいしく乗り切れるタンパク質中心のレシピ「トマト煮ひよこ豆添え 魚のナッツフライ」をご紹介致します。
ぜひお試し下さいね。

こんにちは!
料理家の吉田由子です。
まだまだ残暑が厳しいですね
ビールがおいしいです (笑)
(笑)
ビールのお供であるおつまみは、ささっと作れてヘルシーな物がいいですよね
スパイスやハーブなど、少しパンチのある調味料をプラスすると、シンプルなお料理もお酒のすすむ一品に変身します。
さて、今回はおつまみ作りにおすすめの調味料『ハーブソルト』についてご紹介します。

 『ハーブソルト』は、岩塩や粗塩、こしょうやニンニク、バジル・オレガノ・タイム・マジョラムなどのハーブを乾燥させてブレンドした物です。
『ハーブソルト』は、岩塩や粗塩、こしょうやニンニク、バジル・オレガノ・タイム・マジョラムなどのハーブを乾燥させてブレンドした物です。
ハーブを育てていらっしゃる方は、お好みの配合で手作りしてもおいしいですし、スーパーや輸入食材店などでもいろいろな種類のハーブソルトが販売されています。
私が愛用している物は、岩塩、ペッパー、オニオン、ガーリック、タイム、セロリ、オレガノがブレンドされた物です。
舐めてみると、スナック菓子のような・・・身体に良くなさそうな・・・
感じなのですが、人工的に作られた化学調味料などは入っていません
ハーブや香辛料の風味で十分おいしいので、
ハーブソルトを選ぶときは化学調味料が加えられていない物がおすすめです。
ゆでた野菜やサラダなど、シンプルなお料理にプラスするとたちまちお酒の進む一品に変身しますよ。
お試し下さいね
さて、今回は『ハーブソルトのアンチョビポテト』のレシピをご紹介致します。
ハーブソルトがアクセント!
おつまみにぴったりのレシピです

こんにちは、料理家の野上優佳子です
今年は暑くて長い夏ですが、夏バテなどなさっていませんか
暑いときに食べたくなるのが、エスニック料理
辛さや香りがたまりませんね
ところで、「エスニック料理」って何気なく使っているけど、実際どういう意味なのでしょう

 そもそもエスニックとは英語の【ethnic】が由来となっています。
そもそもエスニックとは英語の【ethnic】が由来となっています。
辞書を見ると、「民族の、民族的な、(少数)民族〔種族〕に関する、異国の」といった意味があります。
英語の【ethnic foods】で料理関連のサイトを見てみると、ネイティブアメリカンの料理をはじめ、メキシコやイタリア、エジプト、アイルランド、ドイツ、インド、タイ、中東、中国、日本、中南米からヨーロッパ、アジア、アラブ、アフリカ大陸など自国以外の様々な地域の国の料理が紹介されています

一方日本で言う「エスニック料理」とは…。
皆さんはどの国を思い浮かべますか?
やはり、タイやベトナム、インドネシア、マレーシアなど東南アジアの国々が最初に挙げられます
インドをはじめとする南アジア料理、トルコやイラン、モロッコなど中近東の料理もそうですね。さらに加えるなら、アフリカ料理もでしょうか。
調べてみると日本では明確な基準はないそうで、自国以外の料理というよりは、中国以外のアジア圏の料理を総じて「エスニック料理」と呼んでいるようです。
面白いのは、イタリアやフランスなどのヨーロッパ圏の料理よりもアジア圏の方が距離や文化的に近いにもかかわらず、「異国の」料理として日本では漠然と認知されているということです
庶民に外国料理が普及したのは明治維新が大きな契機と言えるでしょう。 文明開化により、肉食を取り入れた洋食文化が浸透し始め、大正時代には中国料理、さらに昭和の第二次世界大戦後には朝鮮料理が普及しました。
文明開化により、肉食を取り入れた洋食文化が浸透し始め、大正時代には中国料理、さらに昭和の第二次世界大戦後には朝鮮料理が普及しました。
さらに、高度成長期真っ盛りの1969年には、新宿・中村屋にフランス料理・中国料理・インド料理のメニューを揃えた「民族レストラン」もオープンしました。
そしてアジアへ渡航する観光客の増加により、平成元年頃には一気にエスニック料理のブームが到来し今に至ります。
世界屈指の豊富な外食文化を持つ日本 ゆえに、家庭料理にもそれが反映され、私たちは日頃から様々な味を楽しむことができるのですね
ゆえに、家庭料理にもそれが反映され、私たちは日頃から様々な味を楽しむことができるのですね
さて、本日は辛みと酸味を利かせた「エスニック風シーフードサラダ」をご紹介します。
夏バテ解消にぜひ、お試し下さいね




























